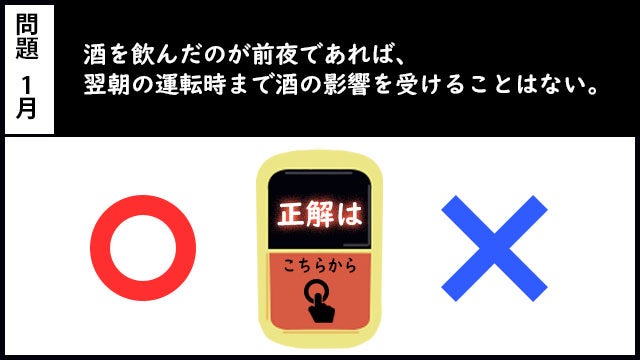未来はここから始まったーー1980〜90年代コンセプトカーが市販化された“伝説の一台”
ジャパンモビリティショー直前特集【前編】…東京モーターショーで生まれた“未来のクルマ”を振り返る2025年10月30日(木)から11月9日(日)に、ジャパンモビリティショー2025が開催されます。今年は「ワクワクする未来を、探しに行こう!」をコンセプトに、国内外の自動車メーカー、部品メーカーなどが出展する予定となっています。
前身の東京モーターショーから、ショーの花形といえば、その時代における未来的デザインや最先端技術を取り入れたコンセプトカーと考えるクルマ好きは多いのではないでしょうか。なかには、ショーでの好評を受け、市販化されたクルマも数多くあります。そこで、東京モーターショー時代に、コンセプトカーから市販化されたクルマたちをピックアップし、解説していきます。
若者たちの遊びのツールとして、クルマが主役だった時代

写真は第24回(1981年)東京モーターショー開催時のもの。当時の開催場所は晴海・東京国際見本市会場。出品台数は歴代最多の849台、来場者数も111万人を超えた
1964年から長年にわたり継承されて来た東京モーターショーという名称を変更し、2023年に記念すべき第1回が開催された、ジャパンモビリティショー。
これまでのような自動車メーカーがメインとなった最新技術や新型車の発表の場という形態だけに留まらず、ドローンやeスポーツといったさまざまな分野のスタートアップ企業の参加に加え、グルメ、アウトドア、お笑いステージなどエンタメ要素の充実化が図られたことで、コアな自動車ファン以外の関心を集め111万人を超える来場者数を獲得。東京モーターショーの名称として最後の開催となった2019年の130万人には及ばなかったものの、海外メーカーの撤退や景気の低迷といった背景から2017年には77万人まで減少していた来場者数を再び100万人ペースに戻すことに成功している。
もちろん、これらは今後に向けたショーの発展という視点から見ても素晴らしい成果と言えるが、先述した自動車ファン(筆者を含む)としては各メーカーの夢と希望が凝縮された個性豊かなコンセプトカーの出品台数が大幅に減少したことについては寂しさを感じているのも事実。とくに1980〜90年代にかけてのショーの主役といえばコンセプトカーであり、それらの中には会場での反響の大きさから市販に至ったものや、部分的なデザインや技術的要素が市販車に生かされた例も少なくなく、その将来像を予想する過程もまたファンにとっての楽しみのひとつでもあった。そこで今回はモーターショーのコンセプトカーから生まれたクルマたちをご紹介。全体的なフォルムやディテールの処理など、ショーモデルとの相違点を探してみるのも楽しい作業かもしれない。
日産/NX-018(1981年出展)→マーチ(1982年登場)
コンセプトカーの形そのままで登場
車両の名称は一般公募で決定

ショーで公開段階から翌年の市販がアナウンスされていたNX-018。このショーでの日産のテーマは「世界に愛される先進技術の日産」というものだった
1977年に登場したダイハツ・シャレードが火をつけたリッターカー(排気量1リットルの車両)市場に打って出るべく開発されたマーチ。日産としては長らくこのクラスの販売モデルを持っていなかっただけに、エンジンや車体まわりなどすべてを新設計。車名も1966年発売のサニー1000に続く一般公募という形が取られるなど、話題作りにも力が入れられていた。当時基本デザインはG・ジウジアーロによるものだったことは噂レベルとされていたが、後年、同社のサイト内でも正式にその関与が明記された。

鮮やかなオレンジのボディカラーで登場したNX-018。広報写真はフェンダーミラーとなっているが、モーターショーの出品車にはドアミラーが装着されていた

ほぼNX-018のままモーターショーの翌年に発売が開始され、10日間で受注1万台のヒットを飛ばしたマーチ。葉書による車名の公募は565万1318通に達した
日産/Be-1(1985年出展)→Be-1(1987年登場)
コンセプトカーの開発テーマは
「ここちよさ優先のナチュラルカー」

初代マーチのFFシャシーをベースに、丸型ヘッドライトの愛らしい車体が与えられたBe-1。現在の目線から見ればレトロ調だが、当時は玩具や文房具のような印象を受けた
1985年の第26回東京モーターショーにて、のちに登場するインフィニティQ45の原型とされる大型セダンCUE-Xや、ミッドシップ4WDの本格スポーツカーMID4など、華やかさや高い動力性能を持ち味とした2台のコンセプトカーとは対照的に、力の抜けたシンプルかつ親しみやすいスタイルで熱狂的な人気を集めたBe-1。車名は開発時のデザイン候補における「B-1案」に由来するものだが、それでは少々味気なさ過ぎるということから、「〜である」、「〜となる」という英語のBe動詞に「1台」という言葉を組み合わせ、「あなたの一台になります」という意味が与えられていた。

ワイパーの本数やドアハンドルの形状などの細部以外、ほぼコンセプトカーのスタイルのまま2年後に発売されたBe-1。PAO(パオ)、フィガロと続く日産パイクカーシリーズの先駆けとなった

広い開口部のキャンバストップや必要最小限のメーター類、棚のようなダッシュボードなど、デザイナーがのびのびと楽しみながら作ったクルマだということがわかる
トヨタ/RAV-FOUR(1989年出展)→RAV4(1994年登場)
オフロードを意識したショーモデルに対し
市販モデルは都会派4駆として登場

車体下部に樹脂プロテクターを用いる手法や、ロールバー状の太いセンターピラーなどは市販版に近いものがあるが、グリル内蔵のウインチや丸型ヘッドランプなど、全体の雰囲気はランクルばりの無骨さが感じられた
文字どおりバブル景気真っ盛りの1989年に開催された第28回東京モーターショー。トヨタ・4500GTやホンダ・NS-X(市販時にNSXへと改名)、スバル・SVX、いすゞ・4200Rなどスポーツタイプのコンセプトカーが続々と登場する一方、活況の兆しを見せつつあったのがRV(レクリエーショナルビークル)と呼ばれていた四輪駆動車。トヨタが発表したRAV-FOURは全長3485mmに対し、ホイールベース2200mmというサンドバギーのようなフォルムが特徴。見た目はコンパクトながら、前方に680mmスライドする助手席とフロア側に回転収納できるリアシートにより、モトクロッサーやマウンテンバイクが搭載できる車内空間が確保されていた。

コンセプトカーの発表から5年後の1994年に発売が開始。発音は同じ「ラブフォー」だが、車名表記はRAV4へと変更。フロントマスクをはじめ、デザインもよりソフト路線となった

雰囲気はタウン志向だが4輪ダブルウィッシュボーン式サスペンションの他、4駆システムもセンターデフを備えた本格的なもので、未舗装路における走破性も秀逸だった
トヨタ/プリウスコンセプト(1995年出展)→プリウス(1997年登場)
エンジン+モーター時代の到来を告げた
エポックメイキングな一台

1995年の東京モーターショーで披露されたプリウスコンセプト。前後のオーバーハングを絞り、広々としたキャビンを確保する手法は市販モデルにも受け継がれた
1968年のガスタービンエンジンを用いたハイブリッドシステムの試作から25年後の1993年。21世紀をリードする画期的な燃費向上技術の確立に向けた「G21プロジェクト」が開発部内に発足。当初はガソリンエンジンの効率を最大限に突き詰めることで既存エンジンの1.5倍という燃費性能の実現を社内目標としていたが、その後「2倍」へと目標値が引き上げられ、エンジンとモーターを組み合わせによるハイブリット方式が浮上。第31回東京モーターショーでお披露目されたプリウスコンセプトは1モーター(量産型は2モーター)で、蓄電装置はバッテリーではなくキャパシタを使用。当時の1.5リッタークラス車の2倍(10・15モードで30km/L)の省燃費性能を謳った。

1997年12月、「21世紀に間に合いました」の名コピーとともに発売されたプリウス。スイッチONで無音、無振動のまま静々と動き出す独特な感覚は、まさに“未来の乗り物”という強烈な印象を与えた
スバル/ストリーガ(1995年出展)→フォレスター(1997年登場)
当時としては奇抜なコンセプトだったのか?
ショーモデルは意外な場所に展示

スバルの自社サイトによると1995年の東京モーターショーでは「乗用車館」ではなく、「商業車館」に展示されていたストリーガ。当時はSUVという呼称が日本国内では一般的でなく、広い荷室と車高の高さだけで商用車風と判断されたのかも?
1981年、2代目レオーネのマイナーチェンジ時に追加されたツーリングワゴン。乗用車と同等以上に充実した装備類や、後部が一段高められたルーフなど「ワゴン=商用車」というイメージの打破に向けた試みは、のちに登場するレガシィ・ツーリングワゴンにおいて結実することに。その一方、ワゴンとSUVとの融合を狙ったコンセプトカーとして、フォレスターの原型となったのがストリーガ。フォレスターのプラットフォームはインプレッサ用だが、こちらはレガシィ用が用いられていたことから、車体はひと回り大柄だった。

ストリーガに対し、穏やかなフロントマスクとなったフォレスター。正式発表の前年には米国・インディアナポリス・モーター・スピードウェイで24時間世界速度記録に挑戦。平均速度180.082km/hを記録している
マツダ/RX-EVOLV(1999年出展)→RX-8(2003年登場)
観音開きの4ドアという新発想で
ロータリーエンジンの延命に貢献

細身の縦型ライトが特徴的なRXエボルブのフロントマスク。力強く張り出した前後のフェンダー形状は市販モデル、RX-8にも継承された
1990年代末期、当時の親会社であるフォードの意向からロータリーエンジンの開発凍結が決定。この動向に異を唱える少数の開発部スタッフたちが極秘裏につくり上げた自然吸気のロータリーエンジンを搭載した手作りの試作車をもとに、製作が行われたのがRXエボルブ。RX-7のような純スポーツカーではなく観音開きの後部用ドアを備え、4人の大人がゆったりと座ることができる車内空間を確保。1999年の東京モーターショーでの公開から4年後の2003年5月にその流れを汲んだRX-8の市販が開始され、2003年4月にRX-7が生産を終えた後も10年にわたりロータリーエンジンの歴史を刻み続けた。

ボンネットとフェンダーが一体となったフロントカウルの導入は見送られたが、フリースタイルドアと名付けられた観音開きのドア構造はそのまま生産車に生かされた

RXエボルブに続き、2001年の第35回東京モーターショーに出品されたRX-8の量産デザインモデルがほぼそのままの形となった生産型。後部ドアをアルミ製とするなど、50:50の前後重量配分を達成していた
自動車が憧れの象徴だった時代
東京モーターショーの歴史

1964年開催の第11回東京モーターショー。海外メーカーの出展もあり、この年から「全日本自動車ショー」から「東京モーターショー」に改名。写真はのちにシルビアとして登場する日産ダットサンクーペ1500
東京モーターショーが初めて開催されたのは1954年のこと。当時の名称は全日本自動車ショウ(英語表記では当初からTOKYO MOTOR SHOWとされていた。1959年より「全日本自動車ショー」に)。会場は日比谷公園内の広場。当然、屋根はなく路面の大部分は土が剥き出しという状態で、一家に一台のマイカー時代の到来前ということもあり、展示車両はトラックやライトバンなどの商用車やオートバイが主流だったが、10日間で54万7000人の来場者を集めた。モーターショーの華とされるコンセプトカーが初めて登場したのは1961年のことで、トヨタからはクラウンのエンジンを搭載した優雅な2ドアクーペ、トヨペット・スポーツXが、ダイハツからは700ccの2ドアセダン、ダイハツ700などが出品され、話題となった。

1989年、第28回東京モーターショーの会場風景。この年から会場が晴海から幕張メッセに移された。この時の来場者数は192万4200人
コンセプトカーから市販に至った“未来のクルマ”特集、いかがでしたでしょうか? 世界的な自動車ショー自体のあるべき姿の見直しや、経済環境の変化などといった要因から昨今では夢や未来を連想させるコンセプトカーの出品台数は少なくなりつつあるようです。その反面、2023年のモビリティショーにおける「プレリュード コンセプト」や「スイフト コンセプト」のように、限りなく生産型に近い状態の車両が出品されるケースは増加傾向にあるようにも思えます。果たしてモビリティショーの名称で2回目となる今回は、どんなクルマたちと出会えるのか? 大いに楽しみにしたいところです。
ジャパンモビリティショー開催直前! コンセプトカーやブース情報はこちらもチェック!
高橋陽介
たかはし・ようすけ 幼少期からのクルマ好きが高じ、九州ローカルの自動車雑誌出版社の編集を経てフリーランスに。雑誌やウェブを中心に、4輪・2輪関連の記事を執筆中。クルマにまつわる映画にも目がない。自身の愛車遍歴はもっぱらマニュアルのスポーツカーだが、後輪駆動とアナログメーターが必須条件のため、購入候補車が年々減っていくのが悩みとなっている様子。
特集の記事一覧

車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ
2026.01.19
~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~
2026.01.13
1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧
2026.01.12
自動車整備技術で日本一に挑む! 自動車整備技能競技大会の舞台裏
2026.01.09
第10回日本カー・オブ・ザ・イヤー。1989年はトヨタ・セルシオを筆頭に高級車の黄金期
2026.01.06
旧車レンタカー・オブ・ザ・イヤー 2025に輝いた一台は?
2026.01.04
昭和・平成を駆け抜けた旧車オーナー珠玉の物語集
2026.01.03