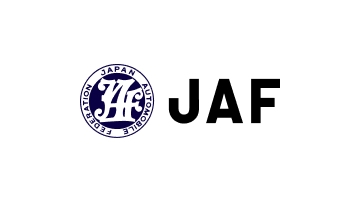トヨタ・セルシオ(初代型)に試乗。世界の高級車市場に影響を及ぼした一台は、いまでも古さを感じさせない #11
自動車ライター・下野康史の旧車試乗記
トヨタが1989年から1994年まで製造していたトヨタ・セルシオ(初代)に試乗。海外市場では「レクサス」のフラッグシップとして開発され、国内ではトヨタブランドで販売、オーナードライバー向け乗用車の新たなフラッグシップモデルとなりました。そんな初代セルシオを自動車ライターの下野康史さんがレンタカーとして借り受け、走りをレポートします。
バブル経済が生んだ、日本車の“決定版”
平成元年(1989年)に登場したトヨタの大型高級セダンがセルシオである。同年1月の米国デトロイトショーでデビューした“レクサスLS400”の国内向けで、ドイツ製高級車に初めて真っ向勝負を挑む歴史的なトヨタ車といえた。開発中には11台の欧州製高級セダンを試験用に購入し、国内外で中古のメルセデスを調べ上げ、各部の摩耗など、耐久性について研究を重ねたと、発表当時、開発責任者のS氏から聞いた。
プレス発表会も凄かった。会場は帝国ホテル最大級の宴会場、孔雀の間。フルオーケストラが待つステージに作曲家の三枝成彰氏が登場し、新型セルシオに捧げる全3楽章の自作曲を披露した。車の御披露目が終わると、ドン・ペリニオンとフランス料理のコースがふるまわれた。セルシオはバブル景気を象徴する日本車の“決定版”だったのだ。
いまなお驚異的な、V8エンジンの静粛性
今回の車も“Vintage Club by KINTO”が用意する期間限定レンタカーである。初代セルシオにはA、B、C、3つの仕様があり、最上級のC仕様だけがエアサスペンション。試乗車はノーマルサスの上級モデル、B仕様で91年式。自動車研究家、山本シンヤ氏の所有車を、トヨタのパートナー企業、新明工業がレストアしたものだ。純正ディーラーオプションのBBSホイールを標準品に戻せば、トヨタ博物館に展示されていてもおかしくないようなコンディションである。
とはいえ、試乗車も32年目、走行6万4000kmを刻んでいる。それを考えると、4リッターV8エンジンの静粛性はいまなお驚異的だ。アイドリングでは、音も振動もない。キーをひねって始動しても、エンジンがかかったのかどうかわからないほどである。
ためしにボンネットを開けて、エンジン上部の平面に500円玉を立ててみたら、立った! 今のクルマのようにアイドリングストップしているわけではない。8本のピストンが上下して、32本の吸排気バルブが動いているのに、だ。
走り出しても、いちばん感心するのはパワートレイン系の“ひそやかさ”である。変速機は4段AT。8速、10速と多段化が進む最新のATからみると時代を感じさせるが、それでも4速トップギアは100km/h時の回転数を1500rpm弱に抑えてくれる。その時もかすかな風切り音が聴こえるだけで、エンジンの存在感はない。発表当時、これは“源流対策”の成果と説明された。音や振動を抑えるのではなく、その源流に遡って、最初から出ないように設計する。30年以上の時を経ても変わらない静粛性に、なるほど“臭いものにフタ”式の小手先の静音設計ではなかったことを実感した。3代続いたセルシオの子孫にあたる現行モデルはレクサスLSだが、パワートレインの静粛性に関して、初代セルシオは最新のLSにもひけをとらない。
ライバル車と比べて控えめなのが初代セルシオらしさ
初代セルシオのボディーは、長さ約5m、幅1.82m。当時、トヨタの最上級パーソナルセダンだったクラウン・ロイヤルサルーンよりもひとまわり以上大きい。しかし、内外装のデザインはむしろ穏やかで控えめに感じられた。やさしい乗り味も含めて、仮想敵だったメルセデスやBMWのようなガツンとくる“強さ”はない。新境地を目指すなら、まずは見た目からもっと自己主張を発揮してもいいのではと感じたものだが、いま見ると、控えめなところも初代セルシオの“らしさ”だったのかなと思う。
自発光式メーターが並ぶ計器盤の片隅で、走行中、常に点滅しているのは、ピエゾTEMSのモニターだ。ピエゾ素子という圧電セラミクスを使って、この車はショックアブソーバーの硬軟を路面状況に応じて変えることができた。その作動状況を見せるチラチラが気になったら、モニターをオフにできるスイッチもついている。
今回の取材でスタッフ一同、いちばん盛り上がったのは、超音波雨滴除去機能付きドアミラーを試した時だった。ドアミラーの鏡に超音波振動を与えて、鏡面の水滴を砕き、ヒーターで加熱して除去する、というもの。ペットボトルの水をかけて試すと、水滴が震えて細かくなり、最後は湯気とともに蒸発してなくなった。タオルでサッと拭けばいいじゃん、なんて言ってはいけない。ゴルフ場の駐車場などで披露してちょっと気持ちよくなったオーナーなどもいたのではないか。初代セルシオが人気を博したあのころは、車のメカや装備に“夢”を感じることができた時代だった。

下野康史
かばた・やすし 1955年、東京都生まれ。『カーグラフィック』など自動車専門誌の編集記者を経て、88年からフリーの自動車ライター。自動運転よりスポーツ自転車を好む。近著に『峠狩り 第二巻』(八重洲出版)、『ポルシェよりフェラーリより、ロードバイクが好き』(講談社文庫)など。
その旧車、レンタルさせてくださいの記事一覧

トヨタ・メガクルーザーの旧車レンタカー試乗記。 “巨大な巡洋艦”の、陸での走りは? #34
2026.01.28トヨタ・メガクルーザー フォトギャラリー #34
2026.01.28ホンダ・インテグラ タイプR(初代・DC2型) フォトギャラリー #33
2025.12.28ホンダ・インテグラ タイプR(初代)のレンタカーに試乗。自然吸気にこだわっていた当時のタイプRの、エンジンの切れ味は? #33
2025.12.28
スバル・インプレッサWRX(初代)のレンタカーに試乗。WRCで天下を取った走りは今でも健在か? #32
2025.11.28スバル・インプレッサWRX(初代) フォトギャラリー #32
2025.11.28TE27レビンの旧車レンタカーの魅力を、豊富な写真とともに解説 トヨタ・カローラレビン(TE27型) フォトギャラリー #31
2025.10.28