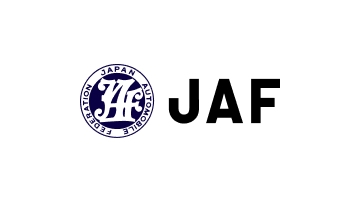トヨタ・セリカ リフトバック2000GT(初代)を箱根で試乗。見た目は70年代スペシャルティカー。でも、扱いやすい! #07
自動車ライター・下野康史の旧車試乗記
トヨタが1970年から77年まで販売していた初代セリカ リフトバックに試乗。“ダルマセリカ”の愛称のクーペとともに記憶に残っている人もいるのではないでしょうか。日本初のスペシャルティカーとしても知られる初代セリカを、自動車ライター・下野康史さんがレンタカーとして借り受け、その走りをレポートします。
Vintage Club by KINTOからお借りしたセリカ リフトバック2000GTは1975年式で、スリーサイズは全長4210mm×全幅1660mm×全高1230mm。車両重量は1080kgだった。静岡県裾野市でのレンタルは終了しており、次は2023年11月から大分で貸し出される予定だ。詳細はVintage Club by KINTOのWebサイト
を参照。
●画像クリックでフォトギャラリーへ
乗りそびれた初代セリカを、レンタカーで乗る
1970年代の車好きに愛されたトヨタ車が、初代セリカである。カリーナと共通の主要構成部品を使ったスポーティーカーだ。フェアレディZのようなスポーツカーを持たない当時のトヨタ車のなかでは、最もスポーティーな量産モデルだったといえる。
70年12月に2ドアクーペで登場したセリカは、73年4月にテールゲートを持つ“リフトバック”を加える。その頃、筆者はまだ免許もない学生だったが、フォード・マスタング・ファストバックに似たリアスタイルを見て、カッコいいセリカが出た! と思ったものである。その後、78年に自動車専門誌の編集部に入った時には、セリカは2代目に代わっていた。そんな“乗りこぼした旧車”も、今はレンタカーで味わうことができるのだ。
快適に乗れるようにレストアされ、“現役感”が漂う
試乗車は以前、スターレット1300Sでもお世話になった“Vintage Club by KINTO”
のクルマだ。今回の貸し出し場所は富士南麓の静岡県裾野市にあるトヨタディーラー。猛暑日にはありがたい屋根付きガレージの下になつかしいセリカが止まっていた。
75年式のリフトバック2000GT。半世紀近い車齢を刻んでいるが、長年このディーラーで面倒をみてもらっているお客さんの車、と言ってもおかしくないような“現役感”が漂っている。ここで貸し出しを始めたのは1か月前からだそうだが、はるばる京都からやってきて、長野まで日帰りで走ってきた人もいるという。
フロントスポイラーやオーバーフェンダーなどを備えるボディーをはじめ、試乗車にはエンジンや足まわりにも改造が加えられている。しかしそれが現代の路上での実用性能を上げる結果になっていれば、けっこうなことだと思う。
ソレックス・キャブの豪快な吸気音で、速さ感が増す
車内にはパウチされた取扱い説明書が載っている。試乗車専用のトリセツである。実際のところ、給油口の場所や、ウインドウォッシャー液の出し方や、ヒーター/クーラーのファンスイッチなどは、この写真入り解説を見ないとわからない。Q&A欄もあって、『ルームランプは点かないのですか?』『点きません。スイッチレバーは壊れて取れています』なんてやりとりに思わず笑ってしまう。
キーをひねると、一瞬、ボソボソッと言ったあと、2リッター4気筒DOHCは元気に目覚める。ソレックスのキャブレターを2基備えるエンジンだが、気温35℃だからチョークレバーを引く必要はなかった。
クラッチペダルは重くない。今のGRヤリスやシビック・タイプRより軽い。つながりのスムーズさを含めて、軟骨のすり減った中高年の膝にもやさしいクラッチだ。5段MTのシフトレバーは長めだが、ゲート感がはっきりしていて扱いやすい。
動き出すと、その走りは豪快だ。『エンジンをいたわってください』というトリセツの指示に従い、回しても4500rpmにとどめたが、街なかではその半分でも十分である。ツインキャブの野太い吸気音のおかげで、実際のスピードより速い“感じがする”のもうれしい。
クルマの進化の過程を知ることができるのも、旧車ならでは
東名高速をひと区間走り、御殿場から長尾峠で箱根に上がる。峠道では3速のまま気持ちよく走れるエンジントルクに驚かされた。湖尻峠からの長い激坂下りでも、ブレーキはヘコたれず、強力に利いた。
ただひとつ気になったのは、昭和のクルマあるあるとも言える“ハンドルの遊び”だ。試乗車は小径のステアリングホイールに換えてあるが、それでも円周上にして10cmくらいの不感帯がある。セリカからはその後、XXが生まれ、さらにスープラへと続く。BMWと共同開発した最新型スープラの正確なステアリングと比べると、さすがに時代を感じさせるが、しかしそんな進化の道程を教えてくれるのも旧車の価値である。
クーラーは付いていたが、スイッチを入れてもあまり効かなかったので、あきらめてペットボトル飲料と塩レモンタブレットでしのいだ。考えてみれば、35℃以上の猛暑日なんて、昭和の昔には言葉からして存在しなかったのだ。ただ、この頃のクルマにはカップホルダーがないから困る。いまやどんなクルマにも標準装備のカップホルダーは、地球温暖化に対する自動車の“適応進化”なのかもしれない。

下野康史
かばた・やすし 1955年、東京都生まれ。『カーグラフィック』など自動車専門誌の編集記者を経て、88年からフリーの自動車ライター。自動運転よりスポーツ自転車を好む。近著に『峠狩り 第二巻』(八重洲出版)、『ポルシェよりフェラーリより、ロードバイクが好き』(講談社文庫)など。
その旧車、レンタルさせてくださいの記事一覧

トヨタ・メガクルーザーの旧車レンタカー試乗記。 “巨大な巡洋艦”の、陸での走りは? #34
2026.01.28トヨタ・メガクルーザー フォトギャラリー #34
2026.01.28ホンダ・インテグラ タイプR(初代・DC2型) フォトギャラリー #33
2025.12.28ホンダ・インテグラ タイプR(初代)のレンタカーに試乗。自然吸気にこだわっていた当時のタイプRの、エンジンの切れ味は? #33
2025.12.28
スバル・インプレッサWRX(初代)のレンタカーに試乗。WRCで天下を取った走りは今でも健在か? #32
2025.11.28スバル・インプレッサWRX(初代) フォトギャラリー #32
2025.11.28TE27レビンの旧車レンタカーの魅力を、豊富な写真とともに解説 トヨタ・カローラレビン(TE27型) フォトギャラリー #31
2025.10.28