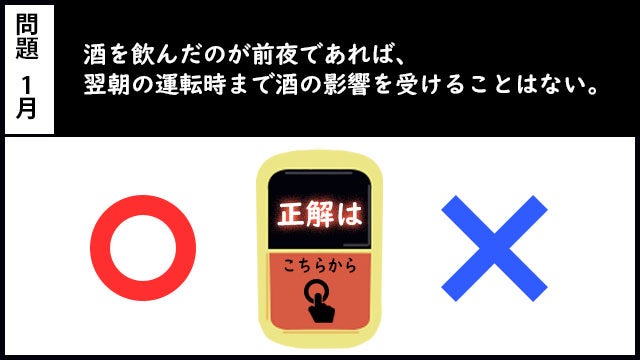街をつなぐのどかな田園風景が続く、新潟県の産業を支えた蒲原鉄道跡を巡る
各地に散らばる廃駅・廃線探訪鉄道をこよなく愛するプロカメラマン徳永茂さんによる厳選された廃線スポットを紹介! 今回は新潟県の加茂(かも)市から五泉(ごせん)市までを結ぶ蒲原(かんばら)鉄道をピックアップ。地元では「蒲鉄(かんてつ)線」と呼ばれ、親しまれてきた路線だ。道路網が発展するまでは生活路線として重要な役割を担ってきた当時の路線をたどる。
新潟県で最初の電気鉄道として開通した蒲原鉄道

JR信越本線との交差部分は、蒲原鉄道の橋梁(きょうりょう)が残っている
新潟県は、江戸時代から物資や人の交流を担う重要な拠点として栄えてきたエリア。大正時代以降は物流も盛んになり、首都圏へつなぐ旅客・貨物の鉄道ルートの他に、拠点ごとの物資輸送や生活基盤のための路線も設けられてきた。
今回紹介する蒲原鉄道は五泉市から加茂市までを結ぶ21.9kmの路線だ。直線的なルートではなく、中蒲原郡村松町(現:五泉市)の中心部を経由し、米穀などの輸送から通勤・通学までを担っていた。

陣ヶ峰(じんがみね)駅跡。築堤の上にはかつてホームがあった

JR信越本線側の橋梁はコンクリート部分しか残っていない

築堤は遊歩道として整備されており、部分的に登ることができる

陣ヶ峰駅跡にはホームの土台だけが残っている

駅跡までは石段が整備され、旧線路まで徒歩で上ることが可能だ
私鉄として1923(大正12)年に開業。新潟県では初めての電気鉄道として開通し、当初は4.2kmほどの区間から1930(昭和5)年に全線開通となった。開業後は1957(昭和32)年以降、輸送量の減少から定期貨物の運用が終了。1963(昭和38)年には豪雪などの自然災害に見舞われることもあった。

加茂農林高校の裏には築堤が残り、かつての線路は駐車場になっている

田園風景の中にあるコンクリート橋もかつては線路だった。こちらの橋台は新しいものだ
路線はその後、利用客の減少にともない、1985(昭和60)年に村松駅から加茂駅までの17.7kmの区間を廃止し、その後、1999(平成11)年10月に村松駅から五泉駅までの全線を廃止した。

かつてあったレールは撤去されている。横を走る道は線路沿いに続く県道9号だ

現在は田んぼ道として活用されているが、当時はこの農道にレールが敷かれていた

狭口(せばぐち)駅跡は、ホームだったことがかろうじてわかるほどしか残っていない

ガーダー橋だった上部に鉄板を取り付けた橋だが、幅は軽自動車でもギリギリだ
線路跡は生活道として活用されている

旧七谷(ななたに)駅は有人駅として、貨物用路線の設備のある駅だった
蒲原鉄道の線路のほとんどは道路として整備されているため、五泉市から加茂市までのルートはたどりやすい。道路のゆるやかなカーブは、当時の線路や車両が曲がれるようなレイアウトを引き継いでいる。
加茂市から加茂川をたどり、県道9号沿いを進むと道沿いに線路があった跡が多く見られる。レールこそ撤去されているが、築堤部分や橋は再利用されていた。
路線上の駅は、土台のみが残っていたり、別の施設になってしまっている場所がほとんど。山間で廃駅跡が残っているのは旧七谷駅のみで、駅舎は集会場として利用されている。島式ホームで旅客線路が2線あり、さらに貨物用にも1線あった駅だ。

レールはすでに撤去されているが、当時のホームの雰囲気は残っている

撤去の際に残されたレールに加え、屋根に使われていた支柱の根本が今も残っていた
当時は、豪雪に備え除雪用のモーターカーも停車していた。冬鳥越方面の山間に向けて勾配も上がってくるポイントだったことがうかがえる。
木造の車体が保存されている冬鳥越駅跡

1954(昭和29)年に現役を引退し、倉庫として使われていた『モハ1』
冬鳥越駅があった場所はファミリー向けスキー場になり、加茂市に譲渡された『モハ1』が展示されている。この『モハ1』は、蒲原鉄道の開業時に投入されたもの。現在、新潟県に残る最古の木造列車だ。2021(令和3)年にクラウドファンディングによって木造の屋根が完成し、車内にも入ることができる。

細長い木材によって、外壁が形成されていることがわかる

車内は当時のままキレイに保存され、レトロな雰囲気を漂わせる

100年以上たった運転台だが、キレイに再塗装されて残っていた
他にも『モハ1』とともに展示されている『モハ61』は、廃線になるまで活躍していた車両だ。車体修復がされ展示されている。

運用されていたときと同じように塗装し直され、保管されている

車内に入ることが可能。シートやつり革など、運用時の名残をとどめている

路線が縮小された際の運賃表がそのまま掲示されていた

運転席の状態もそのままに、間近で見ることができる
この場所では、蒲原鉄道で唯一の電気機関車として貨物輸送を担っていた『ED1』も展示されている。この車両は、蒲原鉄道での貨物輸送が終了する1984(昭和59)年までメインで活躍していた。その後は、工事や除雪などの用途で利用され、蒲原鉄道敷地内にて保管されていたが、加茂市が車両を譲り受けて現在に至る。

『ED1』は旅客車両に比べ、倍以上のパワーがあったことで活躍していた

車内は当時のまま修復されている

この『ED1』は日本車輌製造で、1930(昭和5)年に製造された。貴重なコーションラベルや主要計器が残っており、レバーなどにも触れることができる

実際に運用されていた運転席まわり。とてもシンプルな造りだ
蒲原鉄道の歴史を残す場所は五泉市市街にも!

五泉市村松郷土資料館のある城跡公園には『モハ11』が展示されている
山間から五泉市の市街方面へ進むと、田園地帯から住宅地がメインのエリアになる。町並みの中には路線跡はほとんどないが、五泉市の城跡公園は軌道敷になっていたこともあり、『モハ11』が保存されている。この車両は、2023(令和5)年にクラウドファンディングによって保守されたばかりだ。

屋根付きで保管されている車両。中には入ることができないので、注意が必要だ

車輪まわりもキレイに修復されている

当時使われた踏切信号も残っている

村松郷土資料館の看板を目印にすると、『モハ11形』が展示されているエリアに行きやすい
県道17号沿いにある旧村松駅は、蒲原鉄道の本社ビルに併設され現在も当時の面影を残しながらバスターミナルとして利用されている。当時の駅のホームだった部分は雨よけとして役立っているようだ。奥には倉庫だったエリアが駐車スペースとして残っている。

旧村松駅は廃線後も、蒲原鉄道のバスターミナルとして利用されている

村松駅の表札が残っている蒲原鉄道の本社ビル

村松駅は蒲原鉄道の中心駅だったこともあり、本社事務所の他に車庫などがあった。現在は取り壊され、広い駐車場として利用されている
JR五泉駅には、蒲原鉄道の跡はほとんど残っていないが、現在の駐車場スペースが旧五泉駅の駅舎と線路のあった場所だ。唯一、公衆トイレのデザインに蒲原鉄道を走っていた車両の色が再現されて残っている。

当時の線路は駐車場の通路の場所と合致する

蒲原鉄道を走っていた車両色を再現して塗られている公衆トイレ
今回訪れた蒲原鉄道は、惜しまれつつも時代の流れで廃線となってしまった路線だ。だが、多くの市民から愛されてきたことで、通常なら廃棄されてしまう車両も復元され保管されている。また、線路が県道に沿っていて、比較的探しやすくドライブしながら訪れるのもいいだろう。
今回訪れた廃線の場所はMAPで確認を
特集の記事一覧

宮古島のグルメ完全攻略! 【前編】すべて実食! 島を一周して網羅した厳選3店
2026.01.26
宮古島のグルメ完全攻略!【後編】幻のマングローブ蟹を求め、伊良部島エリアへ! 全実食レポート
2026.01.26
宮古島をバイクで一周! 三つの絶景大橋をコンプリートする旅へ【前編】
2026.01.19
冬の宮古島バイク一周ガイド【後編】ついに!憧れの3.5㎞超の伊良部大橋と日本最南端の天然温泉
2026.01.19
長野―新宿が300円!? 高速バス遠征を極める達人の節約術
2026.01.15
東京“レア”車中泊スポット!23区唯一のRVパークと穴場3選
2026.01.15
初詣ドライブで巡りたい、マニア厳選ユニーク狛犬6選
2026.01.01