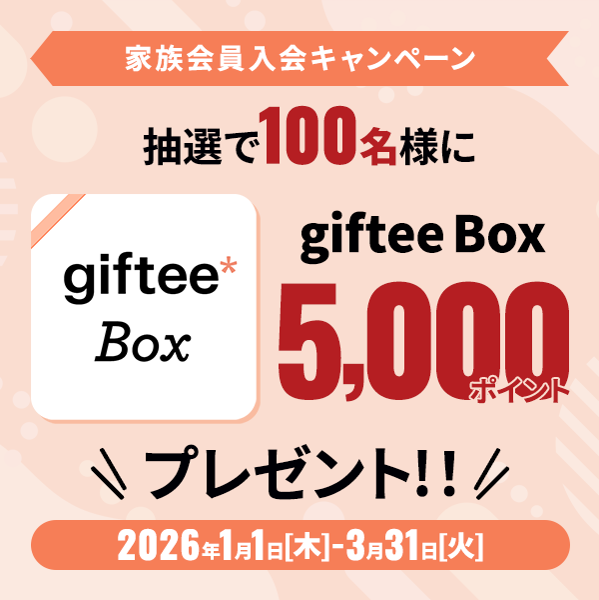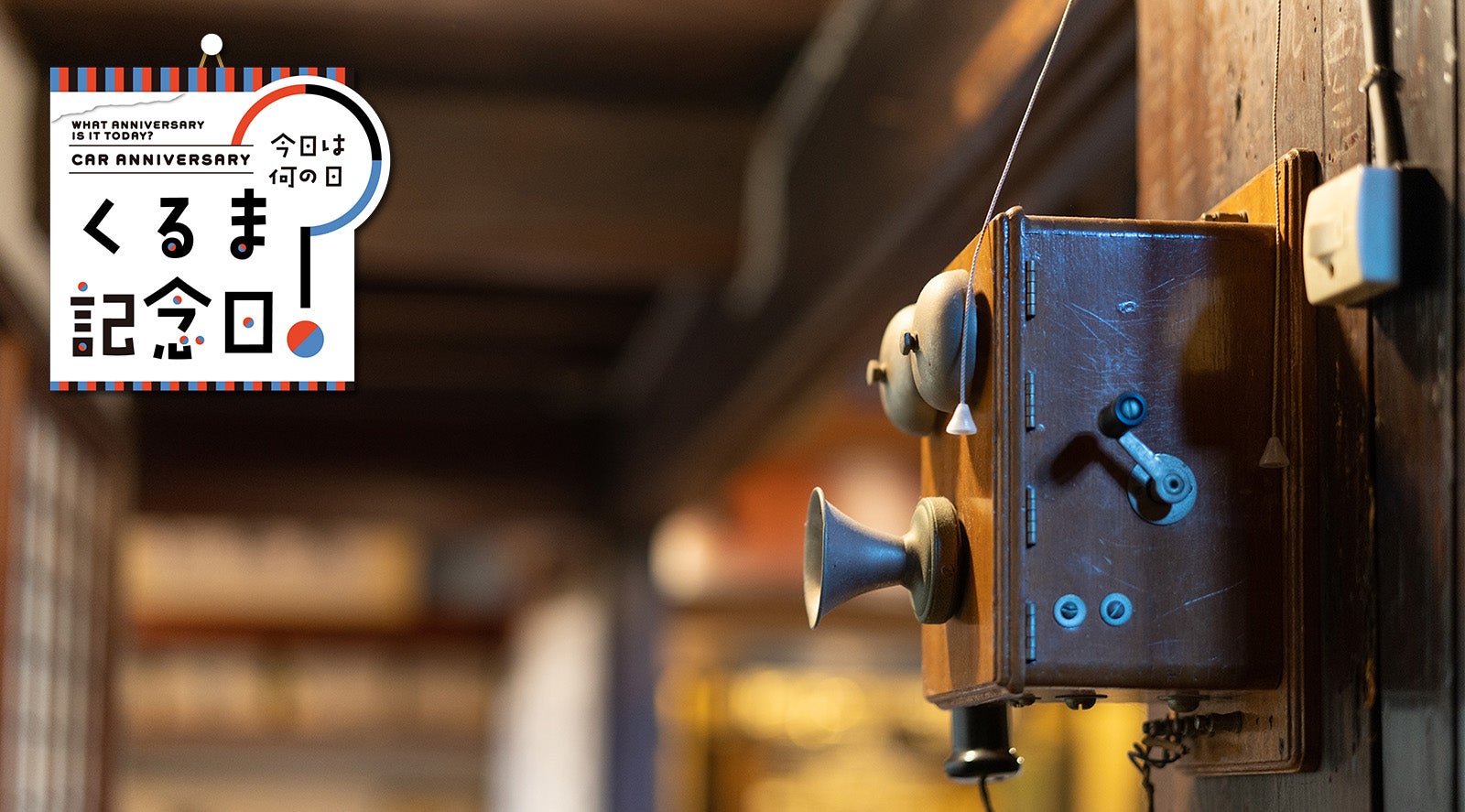土用の丑の日にウナギを食べる風習は江戸時代に始まった。きっかけは平賀源内の大胆な閃き!
知っているとちょっと自慢できるクルマ関連の記念日たくさんの客でにぎわうウナギ店は、日本の夏の風物詩。蒲焼きの香りが漂えば、満腹でも食欲が湧く。なぜ、土用の丑の日にウナギを食べるのか、その風習はいつ始まったのか? 土用とウナギの関係について考えてみよう!
7月19日と31日は「土用の丑の日」
ネットやテレビで情報が流れるので、この日が「土用の丑の日」(どようのうしのひ)であることは多くの人が知っているだろう。この日は古くからウナギを食べる風習がある。発端は江戸時代。本草学者で発明家の平賀源内が、夏場に売り上げが伸びないとウナギ屋から相談を持ち掛けられる。そこで源内が提案したのは、夏の暑い時期に食欲を増進させ、身体を元気にする目的で土用の丑の日にウナギを食べることだった。歴史に名を残す傑物のアイデアは見事に的中。今も続く風習となる。
土用とは、立春、立夏、立秋、立冬の前の各18日間のこと。とくに立秋の前を「夏の土用」といい、土用といえば一般的には夏の土用を指す。丑の日とは、日を十二支で数えたとき丑に該当する日のこと。で、2025年の土用の丑の日は7月19日と31日というわけだ。19日にウナギを食べ損ねた人は、月末にリベンジしてみては?
ウナギに関する情報はこちらもチェック!
東海地方(静岡・愛知・岐阜)のもらって嬉しいお土産ランキング15選
まるでCM!? ドライブ旅をドラマティックに残すためのスマホ動画講座

養殖ウナギの生産量が多いのは、1位が鹿児島県、2位が愛知県、3位が宮崎県(2023年調査)。浜松のウナギで有名な静岡県は、養殖ウナギの発祥の地として知られているが、第4位だ。いよいよ夏本番。旨いウナギを求めてドライブに出かけよう! 写真は静岡県浜松市の浜名湖と浜名湖大橋
この記事はいかがでしたか?
あなたのSNSでこの記事をシェア!