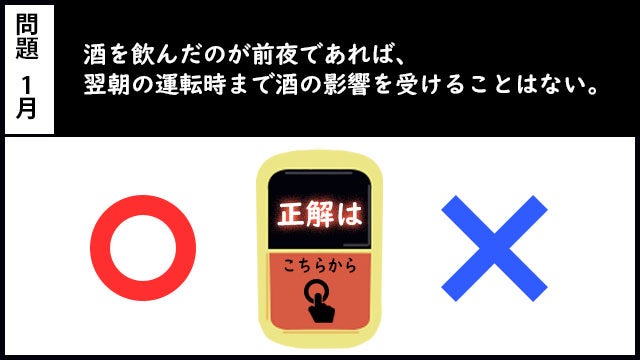今秋にも新型が登場か? ホンダ・プレリュードの歴代モデルを振り返る
オートモビルカウンシル2025で再注目された、プレリュードの系譜と再始動の予感世界のヴィンテージカーが一堂に会する、マニアック系自動車ファン待望のイベント、「オートモビルカウンシル」が2025年も幕張メッセにて開催された。会期は4月11〜13日までの3日間で、過去最高の4万4000人以上の来場者を記録した。
カーデザイン界の巨匠ジウジアーロ氏の来場や伝説的名車ストラトス ゼロの特別展示など趣向を凝らしたプログラムのなか、目を引いたのが、例年以上の規模での展開となった国産メーカーの展示エリア。なかでも歴代プレリュードをテーマとしたホンダブースには多くの人々が足を止めていた。
クルマが遊びのツールの主役だった時代
スペシャルティカーとしての人気を確立
時代を彩った世界の名車がズラリ。出展台数は過去最多の186台に達するなど、開催10年目を迎えるにふさわしい内容となった。国産車メーカーではトヨタ、マツダ、ホンダ、三菱の4社が出展
2023年のジャパンモビリティショーで発表された「プレリュードコンセプト」のデザインがほぼそのまま形となった6代目のプロトタイプ
トヨタ・セリカ、日産シルビア、そしてホンダ・プレリュードという3車がけん引役となり、70年代末期から90年代初頭にかけて一世を風靡(ふうび)したカテゴリーがスペシャルティカー。その定義に具体的な条件は定められてはいないが、スポーツカーのように性能一辺倒ではなく、高級GTカーより価格設定が手頃という“ほどよいオシャレ感”が特徴とされ、主に若者世代からの注目を集めた。なかでも洗練されたオトナのキャラクターで、ライバル勢を一歩リードしていたのがプレリュードだった。
スタイリッシュなフォルムに加えクラス初、国産車初と銘打った数々の新技術や独自の装備類を採用。特にリトラクタブル式ヘッドライトを備えた2代目、3代目モデルは女の子ウケがバツグンということで、ひとクラス上のソアラを凌ぐほどの絶大な人気を獲得。いわゆるバブル景気の後押しもあり、タイトなキャビンにほとんどオマケ扱いのミニマムなリアシートスペースという4人乗りの2ドア車ながら、セールス面において極めて好調な成績を記録した。
その後は景気の後退に加え、クロスカントリータイプの4WDやステーションワゴンといったRV(レクリエーショナルビークル)ブームの到来などによりスペシャルティカー市場は徐々に縮小。プレリュードも1996年に発売された5代目モデルを最後に、長年の歴史に幕を下ろすことに。しかし、すでにメーカーからも正式なコメントとして伝えられている通り、20年以上のブランクを経て、今年の秋には待望の6代目モデルの登場が予定されている。そこで今回はオートモビルカウンシルの会場内に展示されていたプレリュードの歴代モデルを再チェック。各車の持ち味について考察してみた。
初代プレリュード(1978年11月登場)
国産車初の電動サンルーフ搭載車も
展示車両は2分割型のフロントグリルを持つ豪華版のXE。スポーツグレードのXT、XRにはハニカムデザインのグリルを備えていた
145クーペ以来、久々のホンダ製スポーティーカーの登場ということで話題となった初代プレリュード。コンセプトは前席を優先した「スペシャルプライベートカー」というもので、走行パフォーマンスよりあくまで雰囲気重視のキャラクター設定がなされていた。国産車初の電動サンルーフは当初ボディー同色のスチールパネルだったが、1980年1月にはスモークドガラス仕様が追加された。
小ぶりなキャビンが特徴。エンジンはEK型1800ccSOHC4気筒の1種類で、最高出力は90馬力(ホンダマチックと呼ばれたAT車は85馬力)に過ぎなかった

電動サンルーフとともに初代モデルの象徴的装備となったのがスピードとタコを同軸上に配置した集中ターゲットメーター。後発の2代目シビックにも採用された
2代目プレリュード(1982年11月登場)
国産車初の4輪アンチロックブレーキを採用
「FFスーパーボルテージ」というキャッチコピーの通り、インパクト抜群のデザインで登場した2代目。ボレロのBGMとともにゆっくり姿を現すTVコマーシャルも話題に
当時の自動車ファンたちに文字通りアッと驚かすほどの衝撃を与えた2代目モデル。FF車の常識を覆す低さが特徴のボンネットは専用設計のダブルウィッシュボーンサスペンションにより実現可能となったもので、全高自体も1295mmに抑えられていた。リトラクタブルヘッドライトの精悍(せいかん)なマスクも好評を博し、クイントインテグラ(85年2月)やアコード/ビガー(同年6月)にも継承された。
先代譲りのノッチバックスタイルを採用。国産車で初めて4輪アンチロックブレーキシステム(ABS)を装備(XX、XZに装着車を設定。当時の略称は4wALB)されたことでも話題を呼んだ

発売当初は3バルブのSOHCエンジンのみの設定だったが、同クラスのライバル車に対抗すべく85年6月には4バルブヘッドのDOHCエンジンを搭載したSiを追加。大型バンパーやボンネットのパワーバルジなど、外観も専用仕様となっていた
3代目プレリュード(1987年4月登場)
世界初、後輪がステアする舵角応動型4WSを搭載
基本デザインは2代目を踏襲したものだが、ヘッドライト周りの造形がすっきりと一新され、より優雅な雰囲気に仕上げられていた
スーパーヒットモデルとなった2代目の勢いにさらに弾みをつけるべく、1987年に登場した3代目モデル。デザイン自体は2代目の正常進化版と言えるものだったが、注目は世界初採用となった4WSシステム。これは前輪の操舵量に応じて後輪の角度も同位相から逆位相へと変化させることで路面への追従性や小回り性能の向上を狙ったもの。また先代ではリア側はストラットだったサスペンション形式は4輪ともダブルウィッシュボーンとなり、以後数年にわたりこの形式はホンダの看板メカとなっていった。

後方に伸びたスポイラー形状のトランクリッドや極細のCピラーが特徴。1988年にはF1チャンピオン(セナ、プロストがチームを組んだマクラーレンホンダ)を記念した特別仕様車も発売された

映画『地下室のメロディー』のテーマ曲に乗ってキュキュッとリアタイヤが動く映像が話題に。プレリュードの機械式に対し、その後電子制御式となった4WS機構がトヨタ・セリカやマツダ・カペラ、三菱ギャランなどにも採用された
4代目プレリュード(1991年9月登場)
全車3ナンバーボディへとサイズアップ
これまでのすまし顔から一気にアクの強い横長の異形4灯ライトへと転身。70mm拡大された全幅に対し、全高は5mmダウン。全長も20mm切り詰められた
2代目、3代目のイメージを一新。鋭い目つきとマッシヴなフォルムで登場した4代目プレリュード。ボディサイズは全車3ナンバー化。世界初、日本初といったメカニズムや装備面における初モノネタはなかったが、同モデルとして初めてVTEC機構を備えた2.2Lエンジンが搭載された。大幅なワイドトレッド化は運動性能の向上にもつながり、N1耐久レースをはじめモータースポーツの分野でも活躍した。
スパッと切り落とされたテールエンドと縦長のランプが4代目の特徴。ちなみにこのモデルの車名ロゴが、6代目のベースにもなっている

左右につながりを持たせたラウンドデザインのインパネ周りが4代目モデルの特色。歴代プレリュードの定番装備とされてきたサンルーフは、アウタースライド式となった
5代目プレリュード(1996年11月登場)
優れたコーナリング性能を発揮するATTSを搭載
さまざまなデザインにトライする実験車的な印象もあったプレリュードだが、5代目はいたってオーソドックス路線。全高も歴代モデル初の1300mm台となるなど、居住性にも配慮がなされていた
時代の流れや需要の変化とともに2ドアクーペ市場が縮小へと向かうなか、1996年に発売された5代目モデル。シンプルに徹した直線基調デザインは誰もが受け入れやすいものだったが、その反面、スペシャルティカーらしい突出した個性は今ひとつだったようで、残念ながら販売実績的にも成功とは言い難い結果となった。
どこから眺めてもクセのない、プレーンなデザインが5代目モデルの持ち味。4代目に対し居住性のみならず、剛性面も大幅に強化されていた

タイプSグレードにはコーナリング時に外輪側により多くの駆動力を伝えるATTS(アクティブ・トルク・トランスファー・システム)を装備。スポーツ性能的には優れたメカニズムながら、かつての4WSのようにひと目で「スゴイ!」と思えるほどのアピール度に欠けたのが惜しまれる
5世代それぞれに当時の最新技術や画期的な装備が与えられていたプレリュードの変遷、いかがでしたでしょうか。現代的なフォルムをまとい今秋の登場が予定されている6代目モデルにも2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」や「Honda S+ Shift」と名付けられた有段ギア式の変速フィーリングが楽しめる新技術が搭載されているようです。SUVやミニバンがもてはやされているなか、あえてニッチな2ドアクーペの投入に踏み切ったホンダの心意気には一人のスポーツカー好きとして、大いに拍手を送りたいトコロ。公開されたプロトタイプで大まかな概要は知ることができたので、あとは正式な生産型の登場を心待ちにしたいと思います。
高橋陽介
たかはし・ようすけ 幼少期からのクルマ好きが高じ、九州ローカルの自動車雑誌出版社の編集を経てフリーランスに。雑誌やウェブを中心に、4輪・2輪関連の記事を執筆中。クルマにまつわる映画にも目がない。自身の愛車遍歴はもっぱらマニュアルのスポーツカーだが、後輪駆動とアナログメーターが必須条件のため、購入候補車が年々減っていくのが悩みとなっている様子。
特集の記事一覧

車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ
2026.01.19
~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~
2026.01.13
1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧
2026.01.12
自動車整備技術で日本一に挑む! 自動車整備技能競技大会の舞台裏
2026.01.09
第10回日本カー・オブ・ザ・イヤー。1989年はトヨタ・セルシオを筆頭に高級車の黄金期
2026.01.06
旧車レンタカー・オブ・ザ・イヤー 2025に輝いた一台は?
2026.01.04
昭和・平成を駆け抜けた旧車オーナー珠玉の物語集
2026.01.03