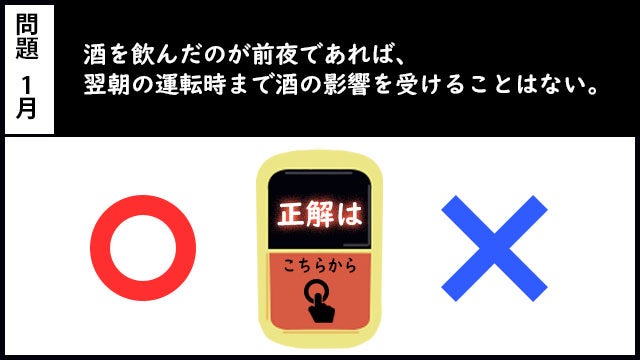運転中の“うとうと”解消法とは? 睡眠研究の第一人者に聞く「眠気対策」
本人も気づかない? 一瞬の眠り「マイクロスリープ」の恐怖
安全運転の大敵、ドライバーを脅かす「眠気」。たとえ一瞬であろうと運転中の眠気は大きな事故につながる危険性があります。
ひと言で眠気といっても、睡眠不足や長時間の運転、病気や薬の副作用など、その原因はさまざま。運転手本人や同乗者、そして歩行者や周りを走るクルマを巻き込まないためにも正しい知識を身に付けておく必要があります。
そこで睡眠研究の第一人者、早稲田大学睡眠研究所所長の西多昌規教授に、眠気の生理的なメカニズム、リスクを高める生活習慣や環境要因、そして科学的に有効な眠気対策について語ってもらいました。
眠気の主な原因は? 異常な眠気は病気の可能性も…

――運転中に眠気が生じる原因について教えてください。
まず一番の原因は寝不足ですよね。ただ十分な睡眠をとっていても運転中に眠くなることがあります。繁華街の近くや街中ならまだ緊張感がありますが、高速道路のような単調な道を走行していると、運転の退屈さから眠気を感じることがあると思います。
体内リズムも眠気に関係しています。大体どの調査でも、昼食後や夜明けあたりの時間帯は眠気がくるので事故率が高くなっています。
それに年齢によっても変わってきます。規則正しい生活をしていれば、夕方頃に最も覚醒度が高くなります。一般に、若年層は朝ちょっと眠気があって夜はシャキッと、逆に高齢になると午前中は頭がスッキリしていますが、午後あたりからだんだん眠くなる傾向があります。
――睡眠不足や体内リズムの乱れは運転にどの程度影響を及ぼしますか?
慢性的な睡眠不足は注意力や判断能力の低下を招きますので、とっさに危険を回避できない、危険なサインを見過ごすといった事態につながります。だいぶ昔の研究ですが徹夜明けは、酒気帯びと同程度に認知機能が低下することが報告されています。いまだによく引用されている研究結果です。
――たとえば毎日3時間程度しか眠れていない人が、旅行で長距離を運転するため前日に7時間寝たからといって安心はできませんか?
その場合は慢性的な睡眠不足ですので睡眠の補充にはなりますが、あまりに寝過ぎてしまうと、今度はリズムを崩すことになるので、これも良くありません。普段から規則正しい生活を送る必要があります。
――病気が眠気の原因ということもありますか?
「ナルコレプシー」という過眠症の病気もありますが、原因として一番考えられるのは「睡眠時無呼吸症候群」です。
中高年の方には睡眠時無呼吸症候群の方が相当数いると考えられます。日中に異常な眠気を感じるとか、若い頃に比べて居眠りが気になるという方は、まずは検査をしたほうがいいかもしれません。
最近では、いびきを記録・測定するスマートフォンの検査アプリもあります。スマホアプリは医療機器ではないため精度は十分ではありませんが、セルフチェックすれば病院に行く目安にはなると思います。この病気に関しては社会問題として取り上げられることも多く、鉄道会社や大手の運送会社は過剰なぐらいチェックをしているところもあります。
患者さんは体質的に肥満傾向にある方が圧倒的に多いのですが、年をとって気道の軟骨の柔軟性が落ちるなど老化が原因でなるケースもあります。
本人も気づかない⁉「マイクロスリープ」の危険性
科学的に有効な眠気対策は

早稲田大学睡眠研究所所長 西多昌規教授
――うとうとする前に眠気を察知する方法はありますか?
サインとしては「マイクロスリープ」というのがあって、いわゆる“こっくり”して、目は開いていても脳が一時的に睡眠状態に陥る状態ですね。厳密な定義があるわけではないのですが、こっくりしないまでも、運転している本人も寝ていることに気づかないぐらいのコンマ何秒の睡眠も含みます。
一般的に眠くなると目は左右にゆっくり動くという傾向があるのですが、眠気を客観的にキャッチするというのは非常に困難です。こっくりし始めるとさすがに自覚できると思いますが、その前段階のマイクロスリープだと、自分で認識することは難しいでしょうね。
――ではマイクロスリープに陥る前にできる対策はありますか?
基本的には刺激です。窓を開けて外気を取り入れるとか、ミントのような味覚への刺激、あとは音楽をかけるなどですね。同乗者がいるなら会話も刺激になります。
しかし、大事なのはこういった刺激に頼りすぎないことです。一時的な対策で長時間もたせようとするのはやめて、安全な場所に停車して1分でも2分でもいいから、目をつぶっているだけでも効果があります。できれば短時間の仮眠をとるのが一番良い方法ではあります。刺激で眠気を覚まそうとしても限界がありますからね。
――コーヒーなどのカフェインを含む飲料も眠気対策としてよく聞きますが、効果はありますか?
カフェインは吸収されるまでに時間がかかります。飲んでから15分後程度たってから効いてきますので、眠くなってから飲んでもすぐに効果は感じられないでしょう。
飲みすぎると耐性ができてあまり効かなくなりますので、1日2~3杯ほどにしておくのがいいと思います。そしてカフェインより効果が大きいのはやはり「仮眠」です。
――効果的な仮眠のとり方を教えてください。
「ショートナップ」といって10分~30分程度の短時間の睡眠が原則です。寝過ぎてしまうと逆にぼーっとしてしまうので、長すぎない程度の時間ですね。
長寝しないようにアラームをかけたり、後部座席などで横になると熟睡してしまうかもしれないので、運転席をリクライニングさせて寝るのがいいでしょう。
あとは「カフェインナップ」といって、コーヒーを飲んでから寝ると15分くらいして効いてきたぐらいでちょうど目が覚めます。カフェインの利尿作用でトイレにも行きたくなりますから、仮眠で長く寝過ぎないためにもいいと思います。
寝不足を防ぐよい入眠方法と
本当に“質の良い”眠りとは

――日頃から寝不足に悩む方に向けて、何か良い入眠方法はありますか?
寝つきが悪い理由というのはさまざまで、たとえば仕事で運転席に座ってばかりで筋肉が緊張しているというのもあるかもしれませんし、精神的なストレスや運動不足、午前中にあまり日光に当たっていないということもリラックスできない原因として考えられます。
そういった方には古典的な入眠方法で「漸進的筋弛緩法」(ぜんしんてききんしかんほう)というのがあります。やり方は筋肉にグーっと力を入れてスッと抜く、これを繰り返すだけです。力が抜ける感覚というのは副交感神経を優位にさせるのでリラックス効果があります。
ほかにもランニングや筋トレといった激しい運動ではなく、ストレッチやヨガといった穏やかな運動は副交感神経を優位にし、リラックスにつながるといわれています。
また入浴は、就寝の1時間~1時間30分前にぬるめの湯船に浸かると、体の深部体温を上げ、寝る頃に体の深部体温が自然に下がり、副交感神経を優位にするという点で推奨されています。シャワーに関しては、スッキリして寝やすくなる人もいれば、ますます目が覚めてしまう人もいるなど、それぞれの主観的な感覚が勝るようです。
――そもそも適切な睡眠時間は?
現役世代では7〜9時間の睡眠が推奨されています。一方で高齢者は必要な睡眠時間が短くなるのが一般的で、これは自然な加齢変化です。著しく長時間眠る場合は病気のサインとなる場合もありますが、必ずしも異常とは限りません。年配の方の睡眠時間が短くなるのは自然な変化です。
――眠りの質というのも大事だと思うのですが、どうすれば睡眠の質を高められますか?
就寝前にリラックスする方法は、入眠法のくだりでお話しした通りですが、最近は「睡眠休養感」という概念についてよく議論されています。よく眠れているか本人がどう感じているかという主観的な評価です。
寝起きが悪いという人や、寝ても疲れがとれないという人でも、脳波を測ってみると意外と結果が良かったりと、睡眠に関しては主観と客観でかなりギャップがあることがわかってきました。あまり睡眠に対してネガティブになり過ぎるのもメンタル不調の入り口になりますので、ご自分でストレスを見直していただくということが重要だと思います。
- ※この記事でご紹介しているのは、西多昌規教授による見解です。運転前には十分に睡眠をとり、安全運転を心がけましょう。

西多昌規
にしだ・まさき
早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授。
早稲田大学 睡眠研究所 所長。
東京医科歯科大学医学部卒業。医学博士。国立精神・神経医療研究センター、ハーバード大学客員研究員、東京医科歯科大学大学院助教、自治医科大学講師、スタンフォード大学客員講師を経て、現職。専門は睡眠、アスリートのメンタルケア、睡眠サポート。睡眠障害、発達障害の治療も行う。
特集の記事一覧

自転車に乗って赤信号で交差点に入ったら、車が急ブレーキ! ホッと一安心…ではなく、青切符を切られるかも?
2026.01.26
大雪で車が立ち往生したら……? 命を守る立ち往生対策と本当に必要な備えをガイド
2026.01.21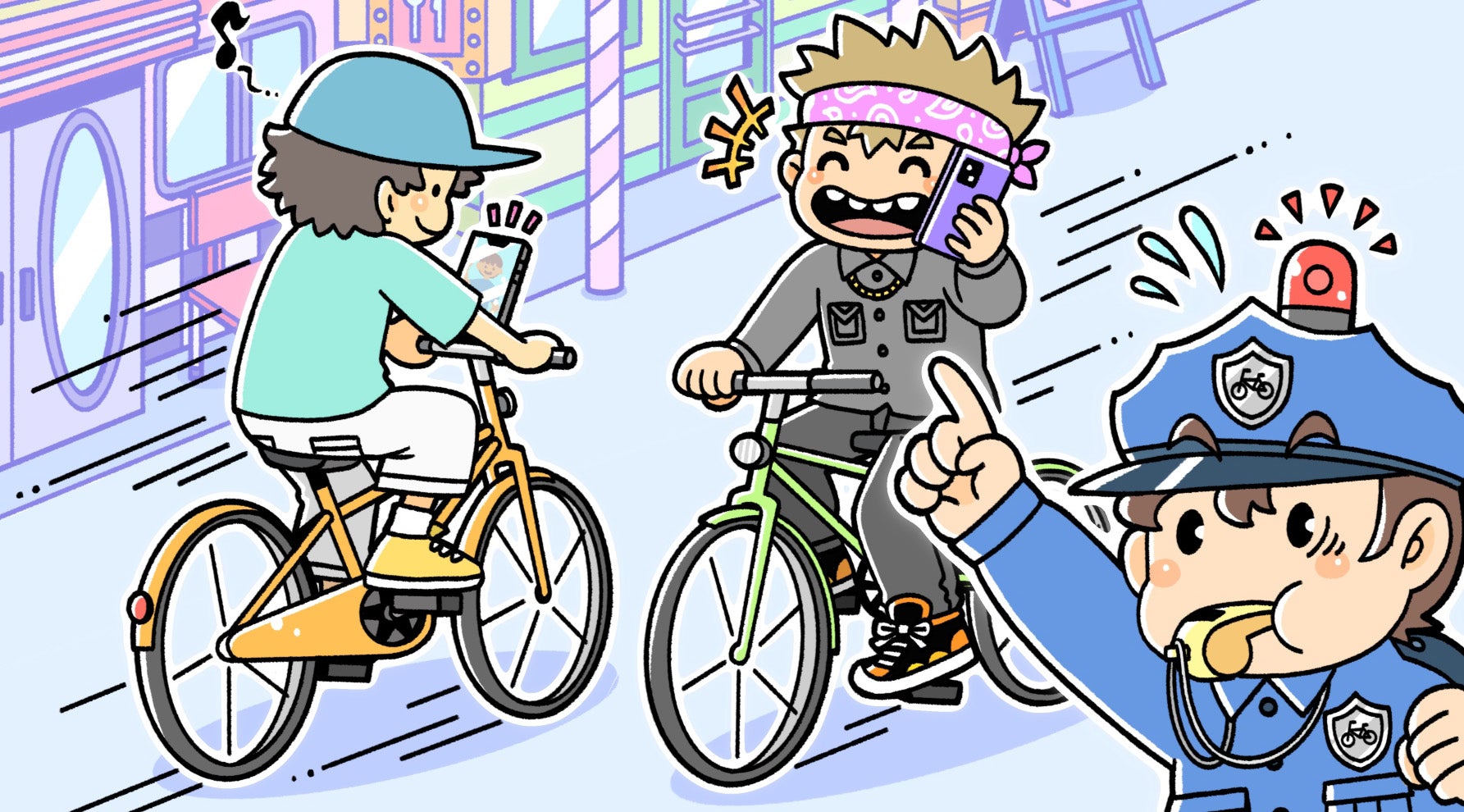
スマホを使いながら自転車を運転。事故リスクの高い「ながらスマホ」は青切符対象!
2026.01.19
2025年の道路交通法クイズを総まとめ!(後編) 1~5位を発表
2026.01.03
大雪で車が立ち往生! 命を守る三種の神器とは?
2026.01.02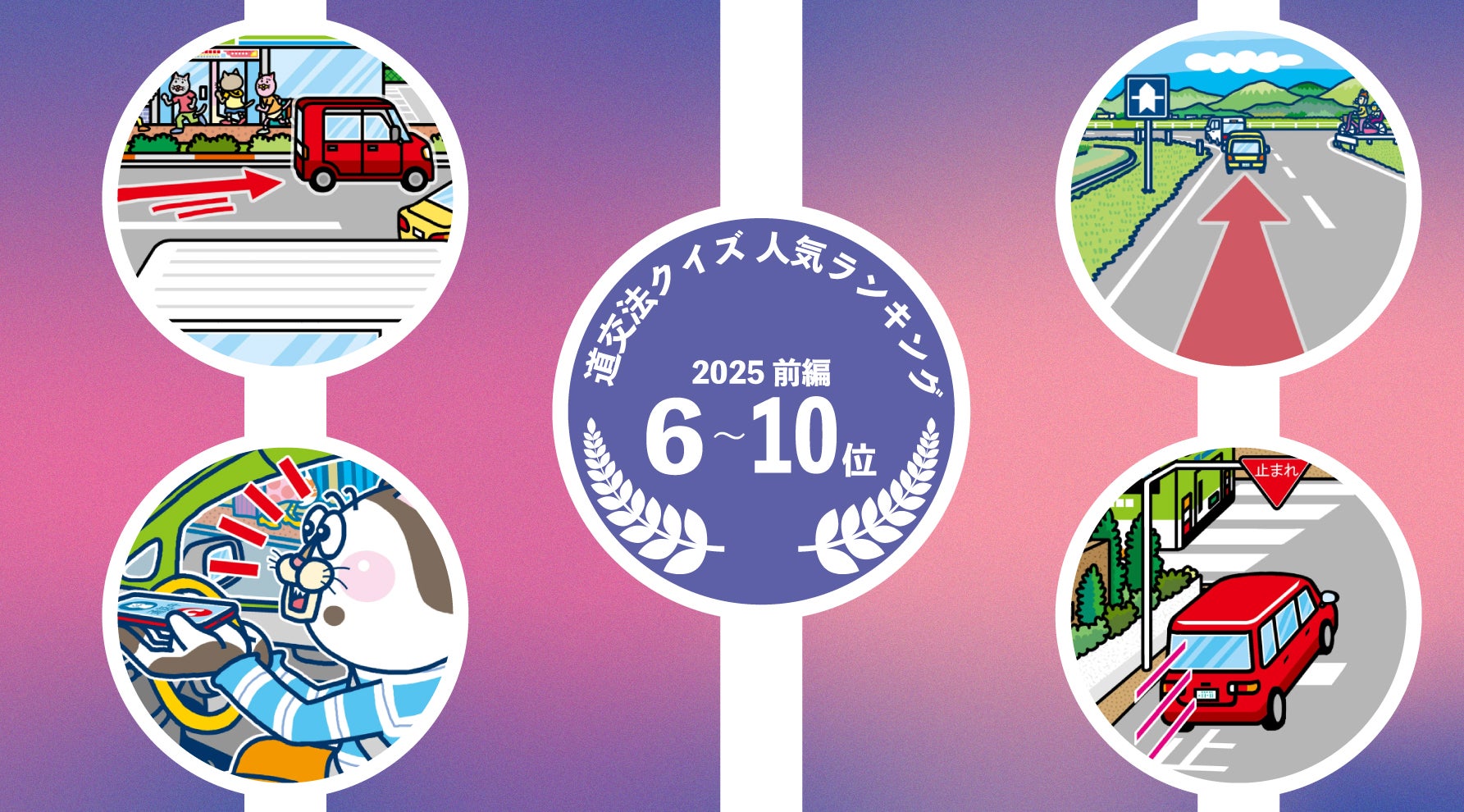
2025年版道交法クイズ人気TOP10をお届け! 前編は10位から6位までを発表!
2025.12.29
冬タイヤを履いても“丸腰”? アンケートで判明した“都会の備え”の盲点と、トランクに備えるべき冬の装備
2025.12.27