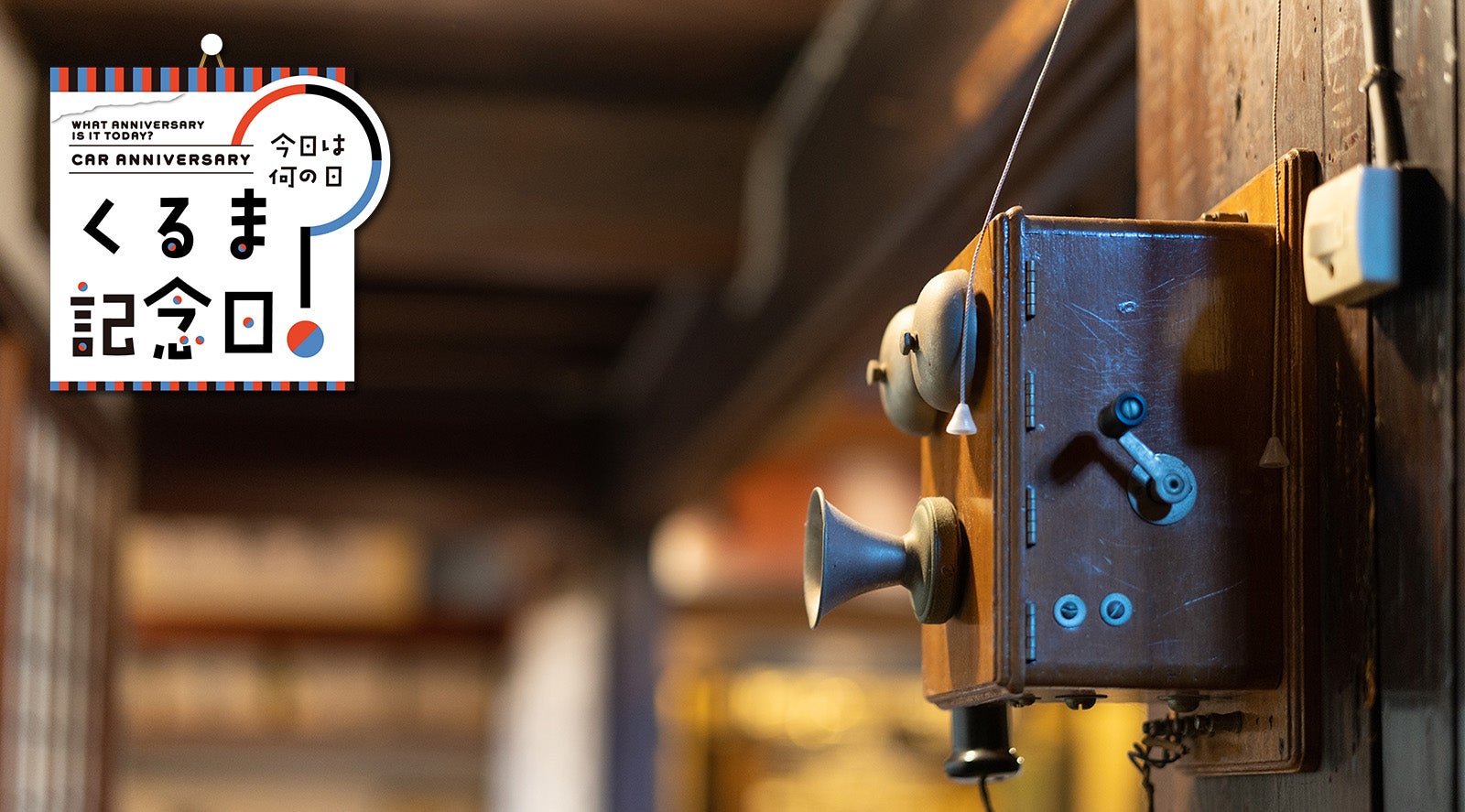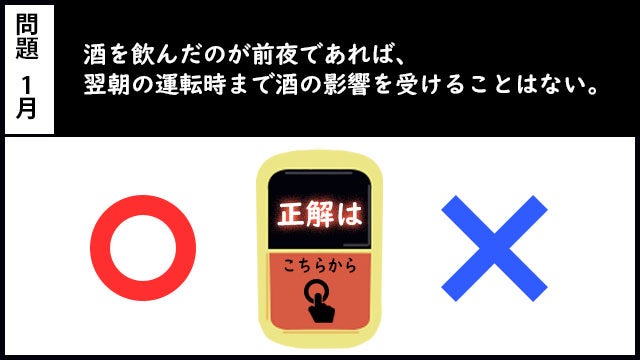11月5日は「世界津波の日」──命を守る高台避難と津波防災の教訓を歴史から学ぶ!
知っているとちょっと自慢できるクルマ関連の記念日津波に対する防災意識を世界的に向上させることを目的に、国連が定めた国際デー。日付は、安政南海地震で、ある男が大勢の村人を津波から救った逸話に由来する。日本では「津波防災の日」としても知られ、全国で避難訓練などが実施される。
11月5日は「世界津波の日」
2015(平成27)年、国連総会で毎年11月5日を「世界津波の日(World Tsunami Awareness Day)」と定めることが決議された。これは1854(安政元)年11月5日(新暦では1854年12月24日)に発生した安政南海地震に由来する。
地震発生後に津波が紀州藩広村(現在の和歌山県広川町)を襲った際、高台に住んでいた濱口梧陵(儀兵衛)が稲むら(屋外に積み上げた稲わら)に火を放ち、火を消そうと集まった村人たちを結果的に安全な高台へと誘導した。この逸話は、パトリック・ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)によって『稲むらの火』として小説化され、津波防災の象徴として語り継がれている。
「世界津波の日」は、濱口梧陵の精神を世界中に発信し、過去の災害から得た教訓を次世代へ伝えることで、津波に対する防災意識を向上させるのが目的。記念日の前後には、内閣府主導の防災訓練やシンポジウムが全国各地で開催され、津波対策の強化を促す。
●津波に関する情報はこちらもチェック!
大地震、津波、台風、ゲリラ豪雨、落雷、大雪…。いざという時に命を守る車の防災
南海トラフ地震に首都圏直下地震…運転中に大きな地震が起きたら、どうすればいいの!?

津波は想像を超える規模で襲ってくることがある。運転中にカーラジオやスマートフォンで津波警報・注意報を見聞きしたら、速やかに海岸や河川から離れ、可能な限り高い場所へ避難しよう。命を守るために、ドライブ先でも避難場所を確認しておきたい