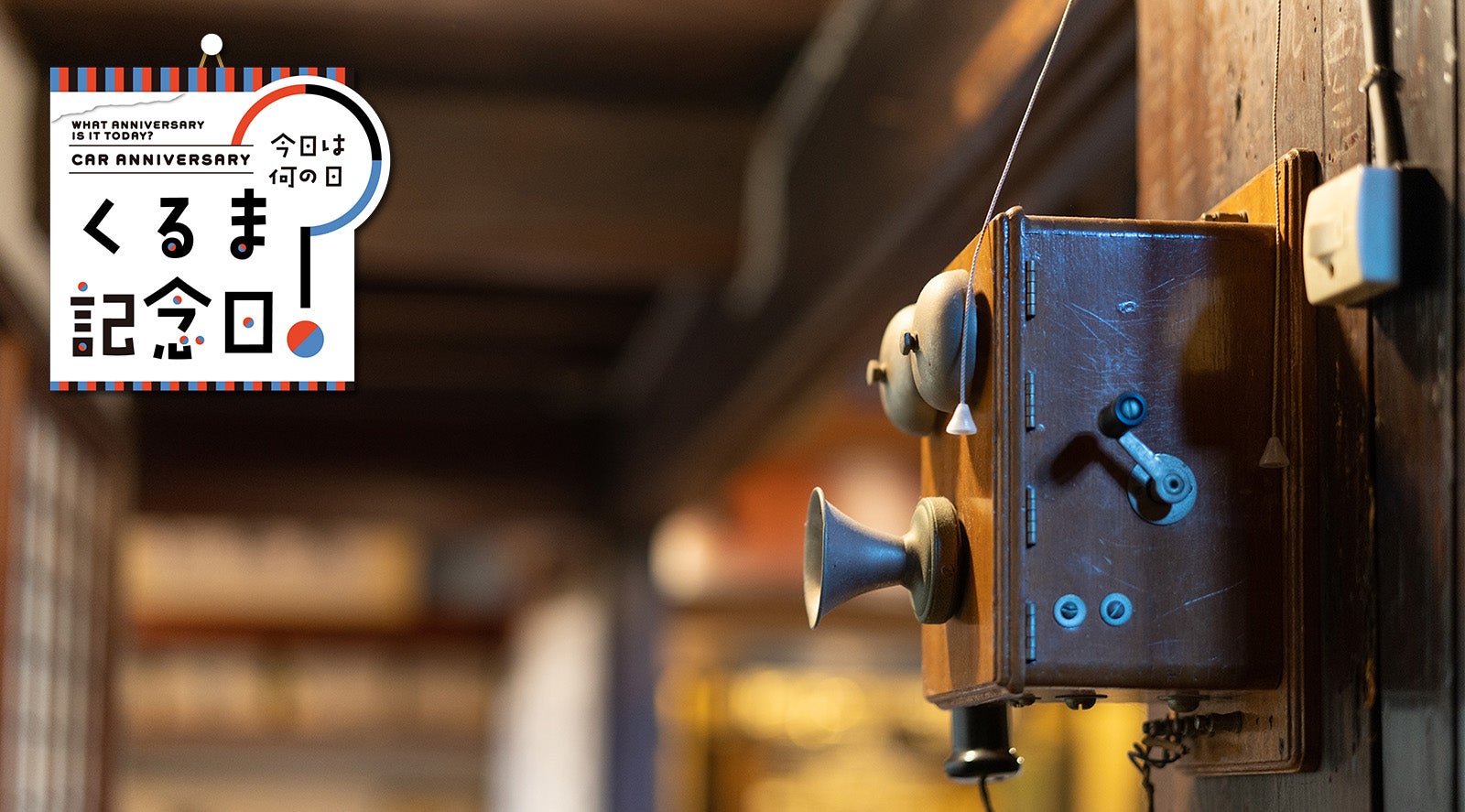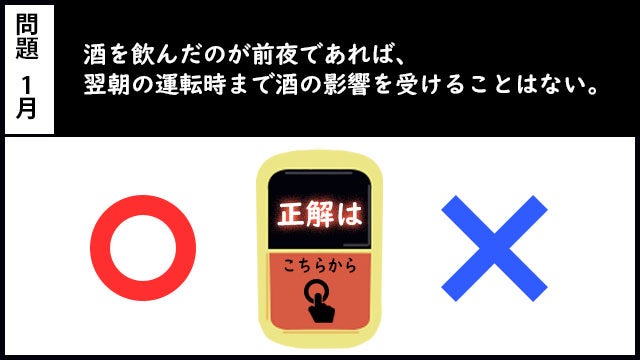うま味調味料は日本の食文化が生んだ大発明! 今や「UMAMI」は世界の共通語
知っているとちょっと自慢できるクルマ関連の記念日うま味とは、甘味、酸味、塩味、苦味と並ぶ5つの基本味のひとつ。料理のおいしさを深めるだけでなく、タンパク質の消化を促進するなど、さまざまな役割を果たす。日本の食文化が生んだうま味は「UMAMI」となり、国際的に使われる言葉になった。
7月25日は「うま味調味料の日」
うま味についての正しい理解と、うま味調味料の普及を目的に、日本うま味調味料協会が制定。昆布出汁(だし)などを口に含んだときに感じる深いコクやまろやかさが、うま味の代表的な味わいだ。その発見は110年以上前の明治時代に遡る。
東京帝国大学(現:東京大学)の池田菊苗(いけだ きくなえ、1864~1936年)博士は、「滋養のある粗食をおいしくすることで栄養補給に貢献したい」との思いから昆布出汁のうま味成分の研究を進め、グルタミン酸がうま味の本体であることを突き止めた。さらに、うま味を使いやすい調味料にすることにも成功。うま味調味料の日は、「グルタミン酸塩を主成分とする調味料の製造法」が特許化された1908(明治41)年7月25日に由来する。
これらの功績により、池田博士は特許庁による「日本の十大発明家」(1985年)にも選出された。なお、かつてうま味調味料は化学調味料とも呼ばれたが、うま味を付与する特性や原料・製法などを正しく表現する名称ではないため、現在は公式に使われていない。
※一般社団法人日本記念日協会認定日
調味料に関する情報はこちらもチェック!
おみやげ土産バナシ
おでんをさらにおいしく! 選抜ちょいかけ調味料5選

1985(昭和60)年の「第1回うま味の国際シンポジウム」で、うま味に関する研究成果が発表されたことをきっかけに英語表記のUMAMIが国際的に浸透した。日本発祥のうま味調味料も、さまざまな国で使われている。写真はうま味のもととなる出汁がとれる食材