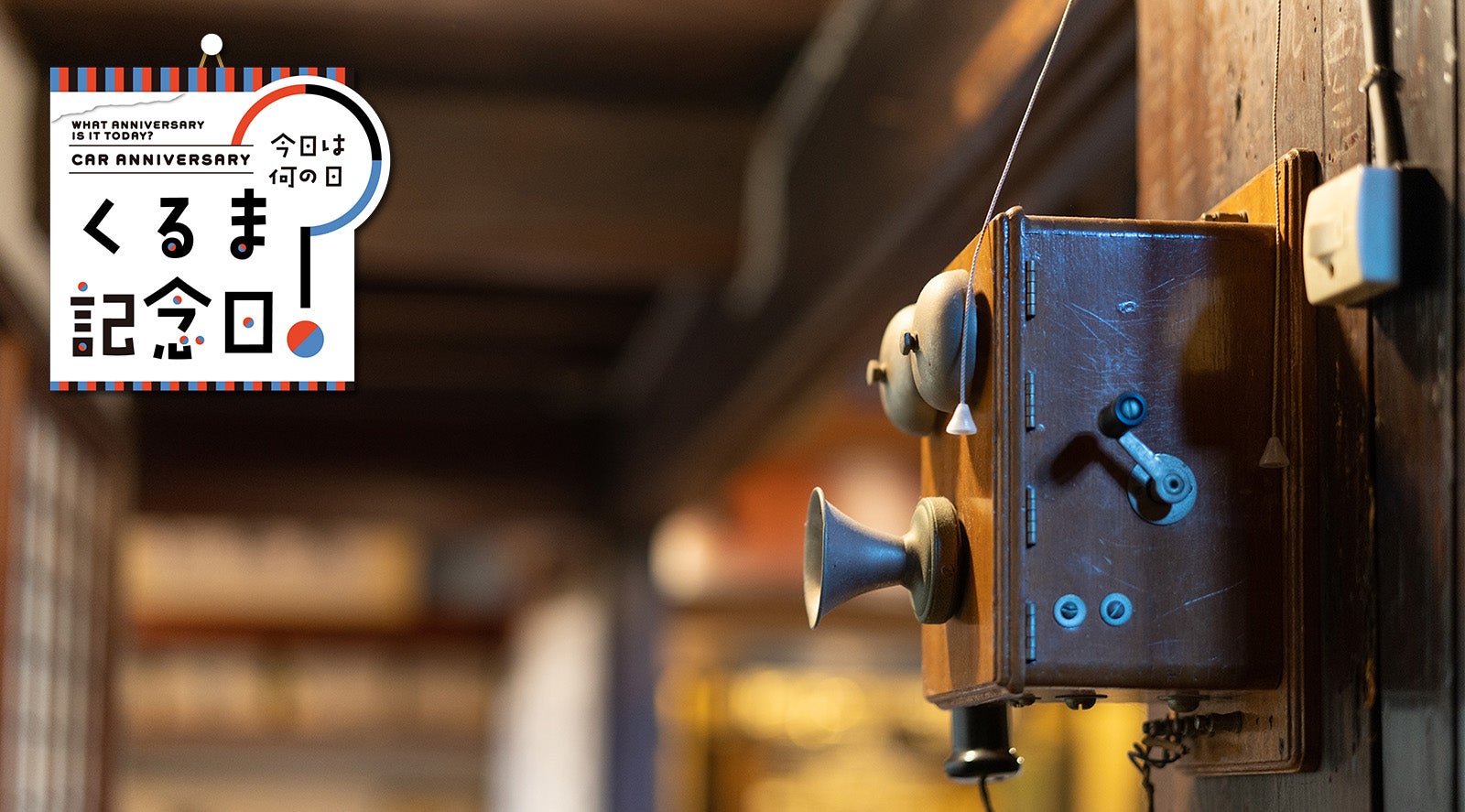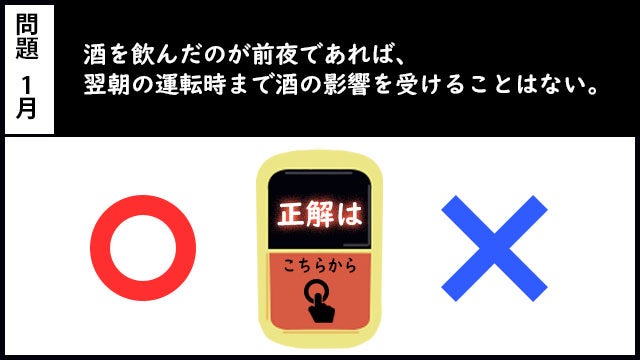今も現役で大活躍? 日本初のケーブルカーは大正7年に奈良県の生駒山で誕生した!
知っているとちょっと自慢できるクルマ関連の記念日日本初のケーブルカーが開業したのは1918(大正7)年。奈良県生駒市と大阪府東大阪市の境にある生駒山に建設された。以後、ケーブルカーは観光客などの移動を助ける交通手段として各地で人気を集めるが、一時的に衰退する。その理由とは?
8月29日は「ケーブルカーの日」
ケーブルカーの歴史や技術、観光資源としての魅力を再認識し、地域の活性化や観光振興を目的に制定された記念日。1918年8月29日、大阪電気軌道(現:近畿日本鉄道)の子会社である生駒鋼索(こうさく)鉄道が、奈良県の生駒山に日本初のケーブルカー「生駒ケーブル」を開業したことに由来する。
ケーブルカーとは、車両につないだケーブル(鋼索)を機械で巻き上げて動かす交通機関のこと。車両に動力を積まないので推進効率に優れ、急な傾斜でも比較的安全に運行できるため、山岳地帯や坂の多い観光地などで利用される。ロープウエーと似ているが、ロープウエーは「空中をワイヤーでつるすゴンドラ」で、ケーブルカーは「斜面を走る車両」を指し、日本では区別するのが一般的だ。

ケーブルカーは大正から昭和にかけて普及。第二次世界大戦の影響で廃止された路線もあったが、戦後の観光ブームで多くが再建された。近鉄の生駒ケーブルは、開業100周年を超えた現在でも運行している。写真は生駒ケーブルの猫型ケーブルカー「ミケ」号
この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!