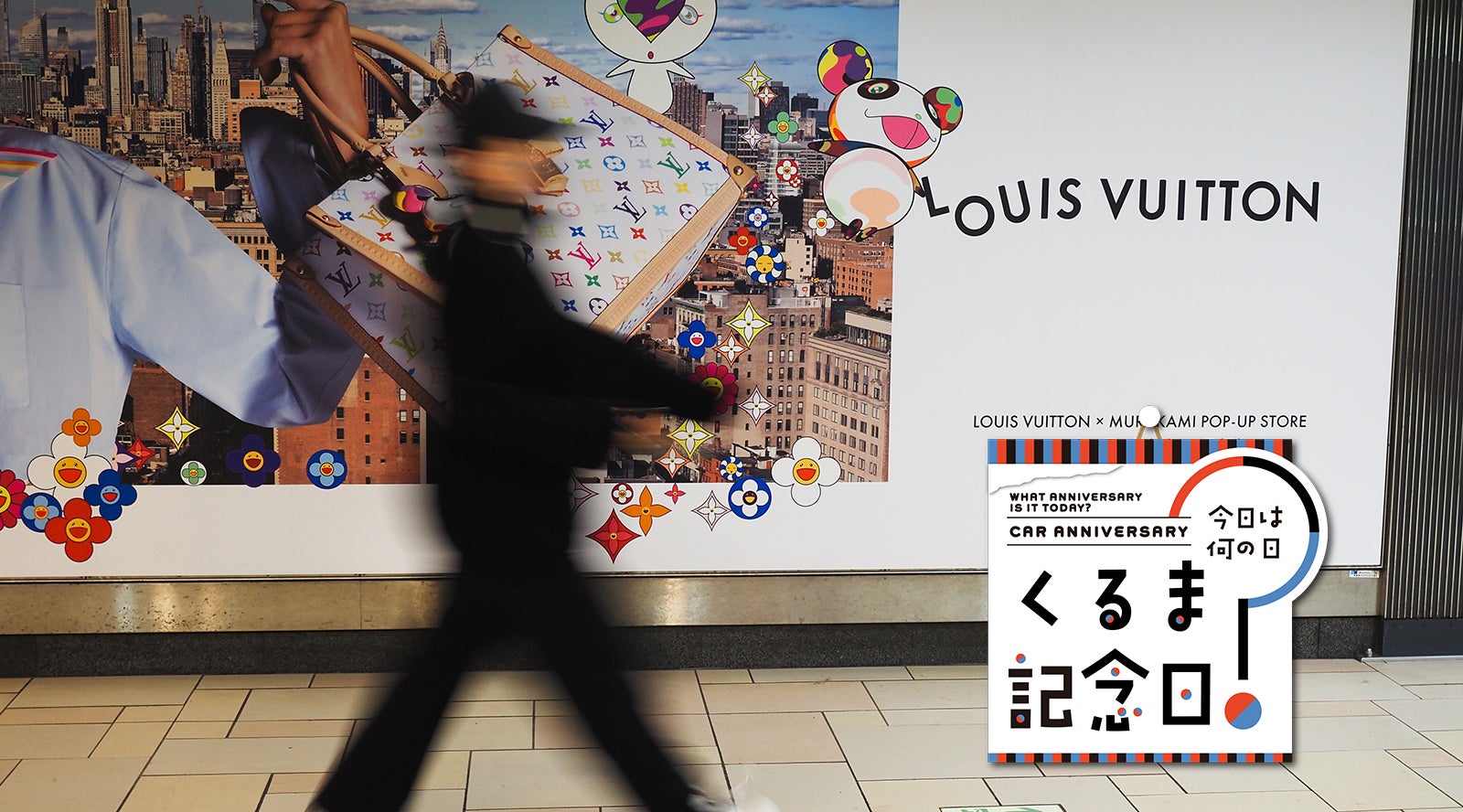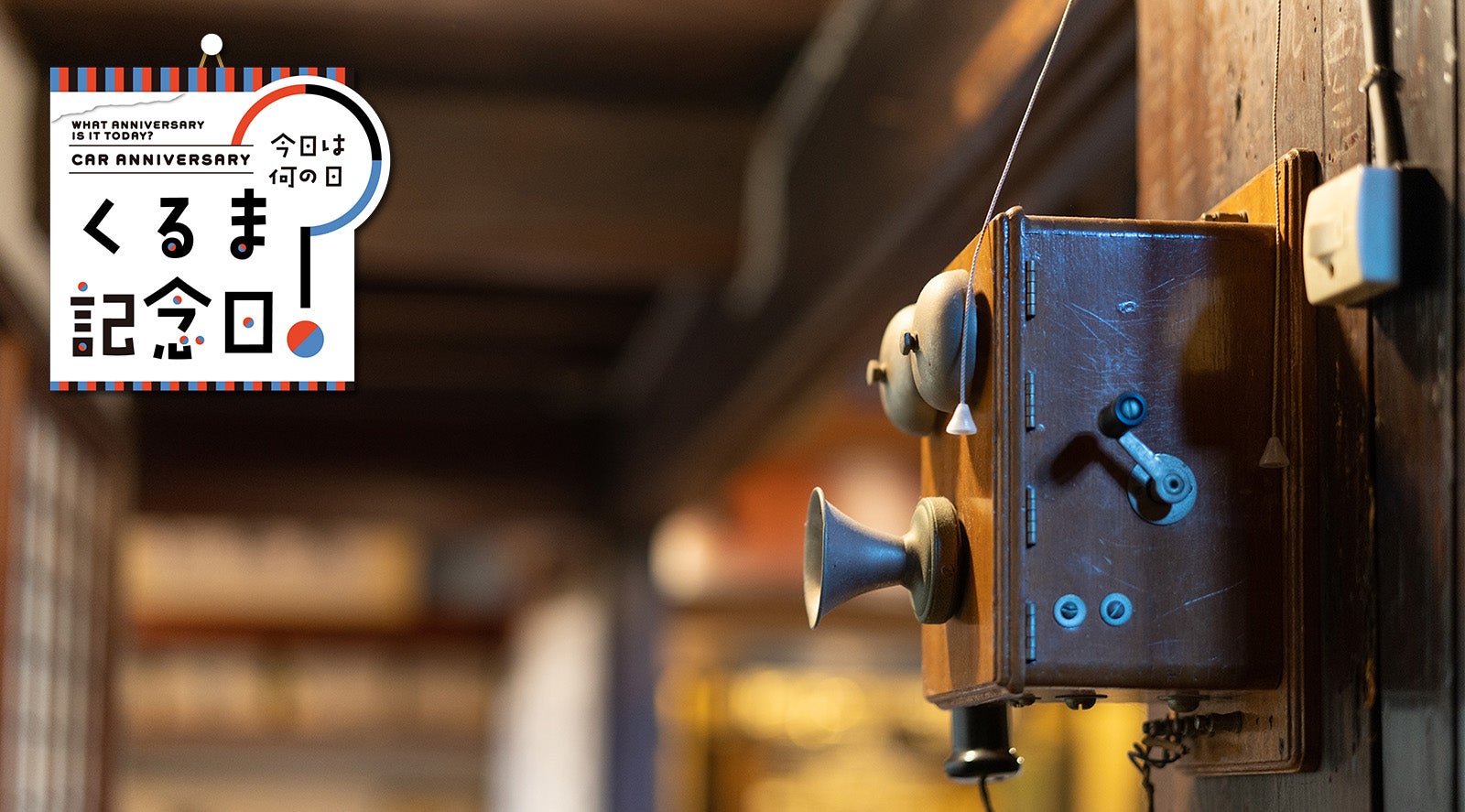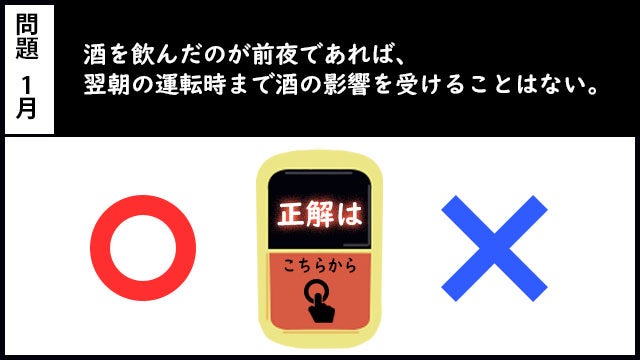電車やバスの車内にある「気になる広告」。効果的な宣伝方法で知られる交通広告の歴史とは?
知っているとちょっと自慢できるクルマ関連の記念日通勤や通学、買い物などで電車やバスを利用するとき、車内で広告を見ることがある。これは一般に「交通広告」と呼ばれるもの。移動中に長時間見ることや、繰り返し露出することで一定の効果が期待できる媒体として注目されている。
5月2日は「交通広告の日」
日本における交通広告の歴史は古く、始まりは1878(明治11)年に鉄道車内に掲示された乗り物酔い止め薬「鎮嘔丹(ちんおうたん)」の広告といわれている。交通広告とは、電車やバスなど公共交通機関の車内をはじめ、駅や空港などの交通関連施設のスペースを利用して掲出される広告媒体の総称。
車体の側面や後部に大きく表示されることが多い「車外広告」や、タクシーの窓や座席背面に設置される「タクシー広告」なども含まれる。雑誌やインターネット広告に比べて人々の目に留まりやすく、高い視認性、繰り返しの露出、長時間の視認などによって一定の宣伝効果が期待できるといわれている。
この記念日は、1993(平成5)年に関東交通広告協議会が制定。公共交通機関における広告の役割や重要性に注目し、その価値を広めることを目的にしている。

交通広告を活用することで、公共交通機関と企業が連携し、地域社会や経済の活性化を図ることも記念日を制定した理由のひとつ。日付の5月2日は、「こ(5)うつう(2)」の語呂合わせから
この記事はいかがでしたか?
この記事のキーワード
あなたのSNSでこの記事をシェア!