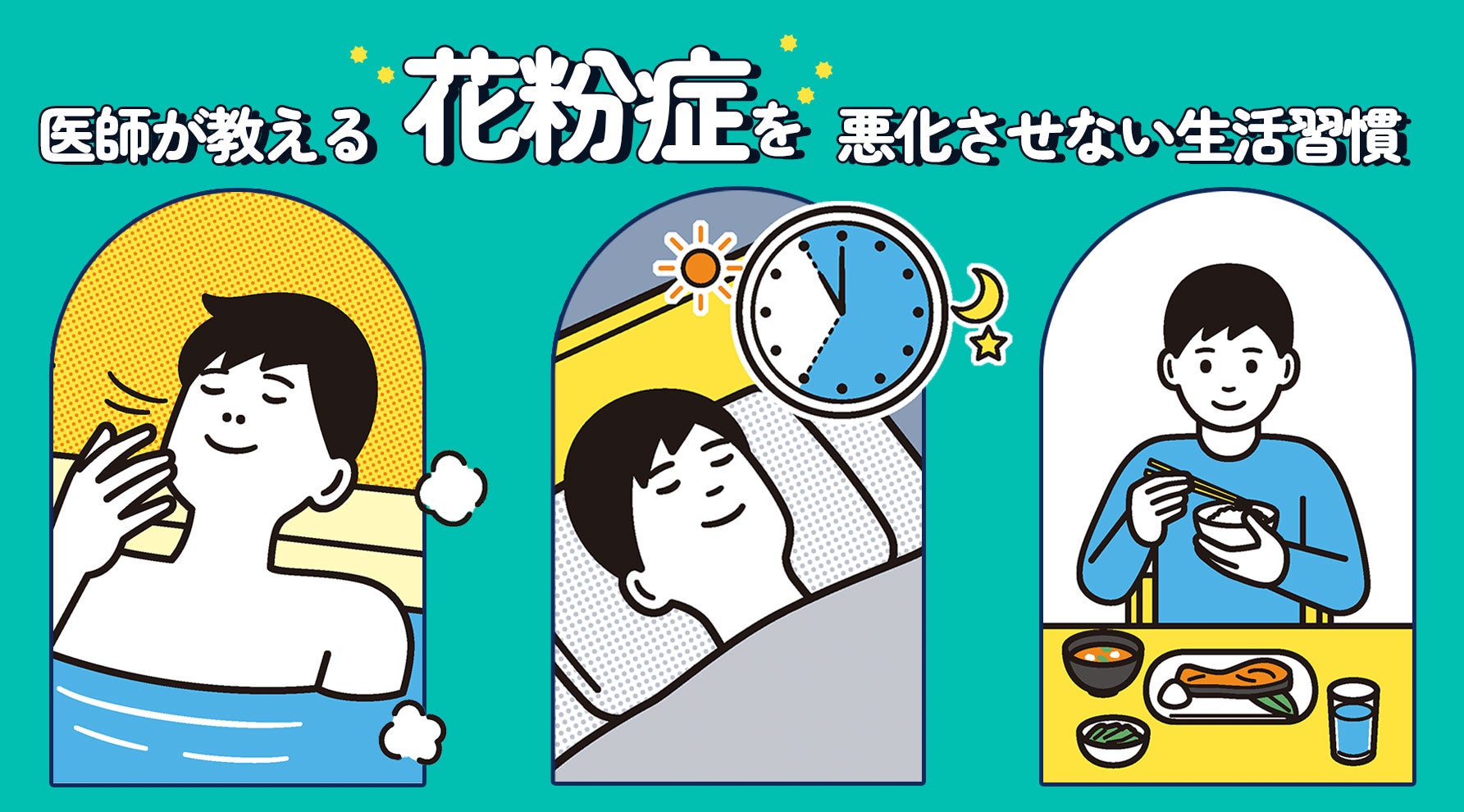睡眠不足・ストレスで花粉症がひどくなる! 花粉症を悪化させない生活習慣を医師が解説
もう花粉症に悩まされない! 花粉症対策で快適ドライブを
鼻水や鼻づまり、目のかゆみなどの花粉症の症状がひどくなる原因は、その日の花粉の飛散量だけではありません。睡眠や休息の不足、ストレスなど、日々の生活習慣も大いに関係しています。症状を悪化させてしまう“ダメ習慣”を、花粉症治療にくわしい大阪はびきの医療センター耳鼻咽喉(いんこう)・頭頸部(とうけいぶ)外科の川島佳代子先生に教えてもらいました。
自律神経が乱れるダメ生活で鼻がグズグズに!
花粉症の代表的な症状が、鼻水や鼻づまりです。鼻は、朝に鼻水やくしゃみが出やすく、夜になるとつまりやすいという特徴がありますが、これらの症状には自律神経の働きが関係しています。
春先は、風が冷たく寒さが身に染みる日もあれば、天気が良く暖かさを感じる日もあります。寒暖差があることでその都度体温を調節する必要があり、自律神経が疲弊しやすい時期なのです。
そんな不安定な季節に、さらに自律神経が乱れるような生活をしていると、花粉症の症状が悪化。今日は鼻のグズグズ・ムズムズがつらい……。そう感じたら、不規則な生活が続いているサインかもしれません。
睡眠不足が続くと鼻の症状が悪化
自律神経が乱れやすくなる原因の一つが、睡眠不足です。よく眠れなかった翌日、鼻水がダラダラ止まらなくなった経験はありませんか。これは、十分な睡眠がとれずに活動モードの交感神経と、リラックスモードの副交感神経のバランスが乱れたから。その結果、鼻水や鼻づまり、くしゃみなどの鼻の症状がひどくなる場合があります。
休日に夜更かしをして就寝・起床時間のずれが大きくなるのもNG。花粉症シーズンこそ、同じ時間に布団に入り、同じ時間に起きることを心がけ、自分にとって適度な睡眠時間を確保しましょう。
夜の習慣でやめたほうがいいのが、湯船に浸からずシャワーでお風呂を済ませること。シャワーだけよりも湯船に浸かるほうがリラックスでき、交感神経から副交感神経に切り替えやすくなります。湯船の蒸気で鼻の通りがよくなるメリットもあるので、呼吸がラクになりスムーズな入眠にも効果的。

ストレスや休息不足も花粉症に悪影響
仕事や家事などでストレスを感じている現代人は多いでしょう。過剰なストレスを発散することなくため込んでいると、交感神経優位の興奮状態が続きます。
リラックスできない日々が続いた結果、次第に自律神経が乱れて花粉症の症状が強く現れます。ストレスをゼロにすることは難しいですが、自分が心地よいと感じる時間を持ち、ストレスが小さいうちに上手に発散しましょう。
休息が少ないことも自律神経のバランスが乱れる要因に。花粉症の症状がひどいときは特に休みをとることを意識して、心身ともにリラックスして過ごすことが症状を悪化させないコツです。
また、花粉症に良いといわれる食品だけをたくさん取る食生活も、あまりおすすめしません。特定の食品に偏るよりも、バランスのとれた食事を1日3食しっかり食べることが大事。自律神経を整える効果はもちろん、免疫力を上げて体調を整える意味でも重要です。

毎年症状がつらいなら病院の受診も選択肢に
「毎年のことだから」と、我慢して春をやり過ごしている人も多いでしょう。鼻水・鼻づまり・くしゃみの3大症状は、運転時の集中力低下につながるだけでなく、仕事や家事などの日常生活のパフォーマンスにも影響を及ぼします。
生活に支障が出ているなら、まずはお近くの耳鼻咽喉科を受診してみてください。病院では抗ヒスタミン薬や鼻に噴霧するステロイド薬など、市販薬と異なる薬が処方されます。重症の場合は、注射で症状を抑える治療もあります。
根本的に改善したい場合は、舌下(ぜっか)免疫療法がおすすめ。これは花粉症の原因となるスギ花粉を原料としたエキスを含んだ錠剤を舐めて少しずつ体内に取り込み、アレルギー反応を弱める治療法。ただし、治療を開始できるのは花粉の飛散が終わった6月以降。ほかにも、鼻の粘膜をレーザーで照射し、症状を出にくくする手術もあります。
このように、病院でできる治療法は複数あります。生活習慣を整えて症状を悪化させないことはもちろん大切ですが、つらいときは無理せず医師に相談を。自分に合う花粉症対策を見つけることが、安全運転につながります。

川島佳代子
かわしま・かよこ 大阪はびきの医療センター副院長、耳鼻咽喉・頭頸部外科 主任部長。アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎などの耳鼻咽喉科領域が専門。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が推進する「花粉症重症化ゼロ作戦」のメンバーとして、花粉症対策や最新治療などの啓発活動も行う。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医・専門研修指導医、日本アレルギー学会指導医。
花粉症重症化ゼロ作戦
特集の記事一覧

もっともっと音楽を身近に 地元を想い、地元に愛される神奈川フィルハーモニー管弦楽団の魅力に迫る!
2026.01.16
旅行やドライブで食べたい! 本当においしい『全国ご当地アイス8選』
2026.01.08
冬アイスランキング決定版! JAF会員が選んだ、昭和から愛される定番アイスTOP10
2026.01.05
ご当地スーパーの絶品鍋5選! 産地直送のあんこう、きりたんぽ、すき焼き、ほうとうをおトクにご自宅で
2025.12.15
帰省土産はコレ! ご当地スーパー「限定PB商品」38選! 年末年始に喜ばれるコスパ最強の絶品お取り寄せ
2025.12.08
ふるさと納税寄附額日本一にもなった"肉と焼酎のふるさと"都城の魅力とは
2025.12.01
運転で目が疲れる人必見! 夏の疲れが残す目の不調を解消する即効ケア5選
2025.11.12