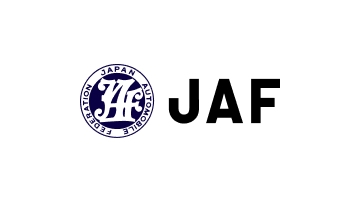117クーペ、アリスト、ランエボも…有名な海外のカーデザイナーが手掛けた懐かしの国産車たち
ジウジアーロやミケロッティ、ピニンファリーナなど近年、クルマのデザインは自社で行うことが多いが、昔はピニンファリーナやジウジアーロ、ミケロッティなど海外の有名なデザイナーやカロッツェリア(デザイン会社)が手掛けた国産車も多かった。いい意味でひと癖あるクルマが多く、注目度も高かった。本特集は、ホンダにおいて数多くのクルマの開発リーダーを務めた繁 浩太郞氏が、そんな海外のカーデザイナーが手掛けた、個性や美しさが際立つ懐かしのモデルを紹介する。
気鋭の海外デザイナー登用で
技術とデザインがせめぎ合い、名車が生まれた

今見ても、はっとするほど美しいデザインのいすゞ・117クーペ。デザインは、かのジョルジェット・ジウジアーロ
戦後再出発した日本の自動車産業は、欧米のクルマをお手本にすることから始まった。つまり、日産がオースチンA40、日野がルノー4CVなどをノックダウン生産することにより自動車の技術を習得した。トヨタは自前開発にこだわり、アメ車等を独自研究し自社ブランド車を造ることを目指した。技術だけでなくデザインも同様に、海外モデルのデザインを参考にしながら、自分たちのデザインを創っていった。
昭和30年代後半あたりから、いよいよ本格的に自社ブランドのクルマの開発~製造に日本の自動車産業は向かう。その際に、ヨーロッパのデザイナーが手掛けたモデルも多くあった。当然、ヒットさせたいという気持ちと、一流のクルマ造りを目指してのことだった。
クルマのデザインとはいっても、クルマはタイヤ、シャシーやエンジンなどのハード部分から出来ているので、デザイナーがカッコ良くするためにボンネットを低くしたいと思っても、エンジンが邪魔でできない場合などがある。つまり、デザインは各カーメーカーの独自のハードや設計要件と整合する必要があるが、当時のカーメーカーはハードを成立させることで精一杯の状態の中、困難な作業だったことと思う。
ヨーロッパにはカーメーカーと比べれば小さな個人的なデザイン会社や工房が多く、そこのデザイナーはカーメーカーの事情をのみ込んで、やり取りできる実力がすでにあった。自動車先進国であったヨーロッパの有名デザイナーに依頼することにより、良いデザインはできるだろうが、中にはデザイナーの持っている価値観とカーメーカーの価値観が合わなかったり、ハードが合わなかったりで、かなり難航したクルマもあったことと思う。つまり、この頃のクルマのデザインは、デザイナーのセンスや意思が反映されているクルマと、デザイナーが妥協(?)したクルマと、その中間というように、大きく3パターンに別れていたような気がする。
デザインは、言うまでもなくクルマの価値を決定づける大切な要素で、より良いデザインを目指すため、当時日進月歩の新技術と抱き合わせで開発するようになり、次第に国内メーカーは自社内でクルマのデザインを行うようになっていく。そうはいっても、自分たちのデザインを見直したりレベルを確認したりするためにも、海外のデザイナーに協力をお願いするクルマもあった。ただ有名ないいデザイナーにお願いしても、簡単にはいかずカッコ良くならなかったり売れなかったりと、デザインは難しい。
大きなエポックとなったのは、「410ブルーバード」つまり「尻下がりのブルーバード」だ。既に世界で有名になっていたピニンファリーナがデザインしたのだから間違いないはずの410ブルーバードの販売が、うまくいかなかった。410ブルーバードはさまざまな教訓を残したと思うが、日産としては次の「510ブルーバード」で後世に残る起死回生のデザインを生んで大ヒットとなった。ただ、このデザインの基本は初代ローレル同様に旧プリンス自動車で行われたと思われる。何と言っても、初代ローレルのデザインと510はよく似ている。
後に、国内各社のブランドとデザインは切り離せなくなり、また国内デザイナーのスキルも十分高くなり、海外デザイナーにお願いすることは減った。また、海外デザイナーは自分たちのブランドを主張するデザインをしがちなので、カーメーカーのブランドにそぐわなくなっていったのかもしれない。
プリンス・スカイラインスポーツ(1962年登場)/ジョバンニ・ミケロッティ(イタリア)

何といっても、キリッとしたヘッドライトとキラキラしたグリルだ。フェンダーミラーが黒いのは、デザイナーが付けたくなかったからと思われる
プリンス・スカイラインスポーツは、生産台数の少なさからあまり知られていないが、そのデザインはジョバンニ・ミケロッティに託されて、個性際立つ高級スポーツカーとして生まれた。
それは、プリンスらしいスポーティーで輝くような美しいデザインとなっている。というか、ミケロッティが後のプリンスデザインの基礎を創ったのかもしれない。
どうしてもキリッとしたつり目のヘッドライトに目がいくが、クルマに必要な一目でわかる存在感を際立たせている。また、後のプリンスに通じるきめ細かなキラキラグリルも特徴的で美しい。
5ナンバー枠サイズでは、どうしても「幅せまヒョロ長ルックス」になりがちだが、後のスカイライン的なサイド面のプレスラインでそれをカバーしている。

後のグロリアにも採用されるが、縦長テールライトで威圧感を感じさせないスッキリとしたスマートなデザインとなっている
いすゞ・117クーペ(1968年登場)/ジョルジェット・ジウジアーロ(イタリア)

奇をてらわない、デザイナーが主張しすぎないなかで、空気を流体と考えた空力デザインで今にも走り出しそうで、また走りたくなるデザインとなっている
ジウジアーロのデザインだが、現実的にはこれだけ美しいスタイルにいすゞのハードを詰め込むのは、相当やり取りしたと思われる。しかし、このデザインを見る限りジウジアーロの妥協した点があるとは感じない。強いて言えば、ルーフの高さだろう。つまりもう少し幅広く長いスタイルをジウジアーロは想定してデザインしたのではないだろうか?
しかし、日本で実車に乗ってみると、細いピラーと広いグラスエリアがすごく壮快だ。今では、衝突安全基準が厳しくなっているので、もうこんな細いピラーと広いグラスエリアのクルマはできないだろう。クルマの進化とは何だろうと考えさせられる。

デザイナーというよりモデラーの力量を発揮した、Cピラー付け根のフェンダーからトランクへの造形美とボディーデザインに合った小さなテールライト周囲の造形には目をみはるものがある
日産・マーチ(1982年)/ジョルジェット・ジウジアーロ(イタリア)

フロント周りはナイフで切り落としたようなスッキリとした面の構成になっている。デザイン的にはどうしようもないフェンダーミラーは黒で目立たないようになっている
日産には元々チェリーという70年発売の1Lの小型FFセダンがあったが、その全長は3660mmと短く、セダンと呼べるデザインになっていなかった。海外ではジョルジェット・ジウジアーロデザインのVWゴルフがビートルの後継車として74年に発売されたが、これはセダンとは異なる大衆ハッチバックの原型となった。日産自動車はチェリーのモデルチェンジ版となるマーチのデザインをジョルジェット・ジウジアーロに任せた。
ゴルフにも通じる直線的でジウジアーロらしいデザインとなったが、時代的にはゴルフが創った大衆車の原型は見慣れてきていたこともあり、マーチのデザインは「普通のハッチバック」という理解に終わったようだ。しかし、「マッチのMarch」というキャッチコピーが評判になり、クルマも良かったのでヒットした。

ゴルフで創られた典型的なハッチバックスタイルを基本に、マーケティングの結果で、より多くのユーザーが受け入れやすいことを重要視したのだろうか
スバル・アルシオーネSVX(1991年)/ジョルジェット・ジウジアーロ(イタリア)

ジウジアーロデザインながらフロント周りのデザインは意外とその特徴は少なく、スバル側でデザインされたのかもしれない
スバルは個性的なデザインであったが国内シェアは小さく、またアメリカ輸出もしていたが現地生産はなくその販売台数は限られていた。そんな中で、アルシオーネSVXという高級(高価格)スペシャルティカーを日本のバブルの雰囲気に乗って、ジョルジェット・ジウジアーロと開発して91年に発売した。
しかし、ジウジアーロのデザインとすぐにわかるほどのシャープな造形は少ない。どちらかというと北米市場を意識したゆったりとして大きく見えるデザインだ。デザインの肝でもあったグラスキャビンだが、ドアガラス等との処理に新技術がなく、高級スペシャル感はあまり発揮されなかった。

リア周りは、ゆったりとしたデザインを横長一文字のテールライトで高級感を醸し出しながら引き締めている
トヨタ・アリスト(1991年)/ジョルジェット・ジウジアーロ(イタリア)

フロント周りはブランド表現なのか他のトヨタ車に近い。筆者としてはジウジアーロらしさをあまり感じなかった
スバル・アルシオーネSVXと全体の存在感がよく似ている。どちらも北米市場を向いて作られたのか、広い荒野でもそれとわかる存在感を表現している。北米市場では手先の細やかな仕事はあまり伝わらない。
また、モデラー領域の面の造りはトヨタ車らしく、全体的にジョルジェット・ジウジアーロがデザインして造られたという部分をあまり感じない。たぶんクライアントであるトヨタの意思がかなり入っているのではないかと思う。

ボリュームと重みのあるリアのデザインは存在感を主張しているようだ
スバル・レガシィ(1993年)/オリビエ・ブーレイ(フランス)

ボンネット、フェンダー、ドア、リアフェンダー、ゲートと続く新しいエモーショナルな面処理とグラスエリアの爽快感は新鮮だった
スバルは、4WDのイメージが強いせいか、もともと「アウトドア」「武骨」というようなコンセプトのデザインが多かったが、93年発売の2代目レガシィではオリビエ・ブーレイが参画して、ワゴンながらより都会的な走り志向の「ツーリングワゴン」というカテゴリーを創った。
基本的には2ボックスのワゴンパッケージングだが、ピラーやガラス処理、ボディー面の造形が新しくエモーショナルで、普通のステーションワゴンではない唯一無二の雰囲気を醸し出している。つまり機能的なだけでなく、カッコイイというエモーショナルなワゴンとなり、「ツーリングワゴン」という新しい名称が似合った。
三菱・ランサーエボリューションⅧ(2003年)/オリビエ・ブーレイ(フランス)

大きな岩にぶつかっても、岩を砕いてしまいそうなほどの強さを感じる。一つの塊としてデザインしているが、ここまで表現できるデザイナーは少ないと思う
このクルマは、力強いフロント周りですべてが完結するが、実はオリビエ・ブーレイというデザイナーは、クルマを一つの塊ととらえてそのクルマをデザインするのがうまい。つまり、部分部分でデザインするのでなく前後側面ルーフまですべてのデザインが整合して一つの塊となっており、それによってランエボの場合は力強さを表現している。
もっと言うと、リアスポイラーやパワーバルジ、フロントグリルの力強い造形にとどまらず、それらを支えるボディーサイドの面の造形まで計算されているのだ。大昔から造形美に触れていないとできないなどと言い訳をしたくなるほど、塊感の表現が素晴らしい。

追従したり追い越したりしようという考えを持たせないほど、圧倒的な威圧感を感じるリア周り
日産・ブルーバード(1963年)/セルジオ・ピニンファリーナ(イタリア)

フロントは当時のアルファロメオのデザインに似ているが、まだ日本でアルファロメオはあまり知られていなかった
イタリアデザイン界の巨匠であり、フェラーリのデザインで知られるセルジオ・ピニンファリーナのデザインとして有名だ。つまり、世界最高とも言えるデザイナーにブルーバードのデザインを託したのだ。
しかし、結果的には、ユーザーの評判は悪く「尻下がり」と言われ、2年ほどの短い間で後ろ周りのデザイン変更をしている。なぜ巨匠と言われるほどのセルジオ・ピニンファリーナが、日本人でなくとも違和感を感じるこの尻下がりを良しとしたのか?
当時の2代目セドリックもセルジオ・ピニンファリーナに託しており、ブルーバードと似ているが、こちらの評価はそんなに悪くない。つまり、今ではよくあるデザインとサイズの問題だ。デザイン発想はいいのだが、ブルーバードでは寸足らずだったということになる。それが量産化までいくということは、気づいたときには引き返せない事情や都合があったのだろう。

フロントから流れてくるボディーのデザインが、リアピラーの後ろのトランク部分で急に下がって、一つのデザインとして見えなかった
トヨタ・ヴィッツ(1999年)/ソティリス・コヴォス(ギリシャ)

唯一無二の新しいエモーショナルなルックスながら、親しみを感じる。つまり、新しくても親しみがあるという二律背反のテーマが、細部にわたるまで一つのデザインとして表現されているということだ
ソティリス・コヴォスはロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートを卒業後、新卒でトヨタヨーロッパにデザイナーとして就職してヤリス(ヴィッツ)をデザインした。その後独立している。やはり天才的なデザイナーなどは、会社という枠が窮屈に思えるのかよくわからないが、このパターンは他のカーメーカーでも多い。
どう考えても日本人にはできないエモーショナルなデザインを小型車でうまく創り上げている。すべての面の造形が豊かで、小さいクルマ=安っぽいクルマという常識を覆している。それでいて、日本の交通環境や街並みにもなじむ。私は基本的に左脳人間ということもあり、こういうデザイナーの力量にはホントに脱帽する。魔術に感じる。
セドリックにもピニンファリーナのフローイングラインを採用
日産・セドリック(1965年)

2代目セドリックのサイドビューは、優雅でジャガーに通じるものがある
ブルーバードと同じく2代目セドリックもピニンファリーナがデザインしている。そのデザインコンセプトは両方ともフロントで存在感を主張し、リアに向けて流れるように収束させるものだ。なのに、410ブルーバードの方は「尻下がり」と評判は良くなかった。
2 代目セドリックの方は、不評というよりは販売台数から見ても成功と言えた。初代が約14.5万台、この2代目が約22万台、3代目が約28.6万台と、順調にセドリックの販売台数は伸びて、クラウンとの競合関係に成長する中で、2代目はキチンとその役割を果たしたと言える。
これは、リアに向けて流れるように収束させるデザインには、セドリック程度の車両の長さ(4680mm)が必要で、ブルーバードの全長(3995mm)では、短すぎたということだと思う。デザイナーのデザインイメージと実際の全長が異なったということではないか? とはいっても410ブルーバードには何か表に出てきていない「尻下がり」デザインになる事情や都合があったような気もする。
いずれにしても、この2代目セドリックのモチーフはジャガーのような気もするが、その優雅で高級感もありながら壮快な走りを想像させるデザインは、セドリックブランドをしっかりと創ったと思う。

ゆったりとした高級感と滑るような走り出しという二律背反とも言える両者を解決したデザイン
デザインではないけれど
カブリオレの開発で技術協力もしていたピニンファリーナ
ホンダ・シティカブリオレ(1984年)

サッシュレスドアにすることにより、カブリオレらしい開放感を出している
初代シティは、若者をターゲットユーザーにして企画された。「トールボーイ」と呼ばれた。そのパッケージは新鮮で、さらにスッキリとしたデザインテイストは、若者に「欲しかったのは、これだ!」と言わせた。大好評だったこともあり、シティターボ、シティターボⅡ、シティカブリオレと派生展開された。
カブリオレ(幌付きオープンカー)は、ホンダS800で経験していたが、その骨組みの設計技術的に機能性とデザイン性を両立させるのが難しく、開発時間も少なかったことから、以前から幌を設計デザインする部門が活躍していたピニンファリーナ社にお願いした。
結果として、幌を畳んだ形から幌を広げてボディーの一部になっている形の両方ともキチンとまとまった形となり、市場でも好評だった。なにしろホンダの他の車両担当など、多くのデザイナーが購入したことからも、いかにいいデザインだったかがわかる。
開発過程で幌とボディーのボリュームにおいて、ボディー側をターボⅡのマッチョなものに変更し、バランスを良くした。さらにボディーカラーもデザインのうちとばかりに、異例の12色のパステルカラーを準備して楽しさを盛り上げた。

幌はボディーの鉄とは異質なために、どうしても見た目のボリューム感が増すが、このデザインはバランスがいい
日本の自動車産業の黎明期に、海外デザイナーと手を組んで個性や美しさが際立ったモデルが数多く開発された。そういった歴史に残ることになったクルマを紹介することで、日本車の今後のデザイン進化の参考になればと筆者は考える。
繁 浩太郞
しげ・こうたろう 京都市出身。ホンダにおいて四輪設計者から開発統括へと企画開発畑を歩き、開発リーダーを務めたクルマの数は自称世界一。その中で代表作は「Honda・CR-X デルソル」。現在はモータージャーナリストとして活躍中。クルマ遍歴はホンダ車以外の古い輸入中古車多数、退職とともにまともなドイツ車に。趣味はオタクなグループサウンズ(GS)で、「GSバンド」を作りリードギターを担当。
特集の記事一覧

2トーンカラー、SUVやハイトワゴンでなぜ人気が復活した?
2026.02.09
3月はクルマ購入の好機!最大数十万円もお得に!?
2026.02.02
希望ナンバーの“本音”が見えた! 数字の人気ランキングと選ばれる理由
2026.01.31
鋼鉄の盾! 自衛隊の輸送防護車「MRAP」とは?
2026.01.29
車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ
2026.01.19
~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~
2026.01.13
1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧
2026.01.12